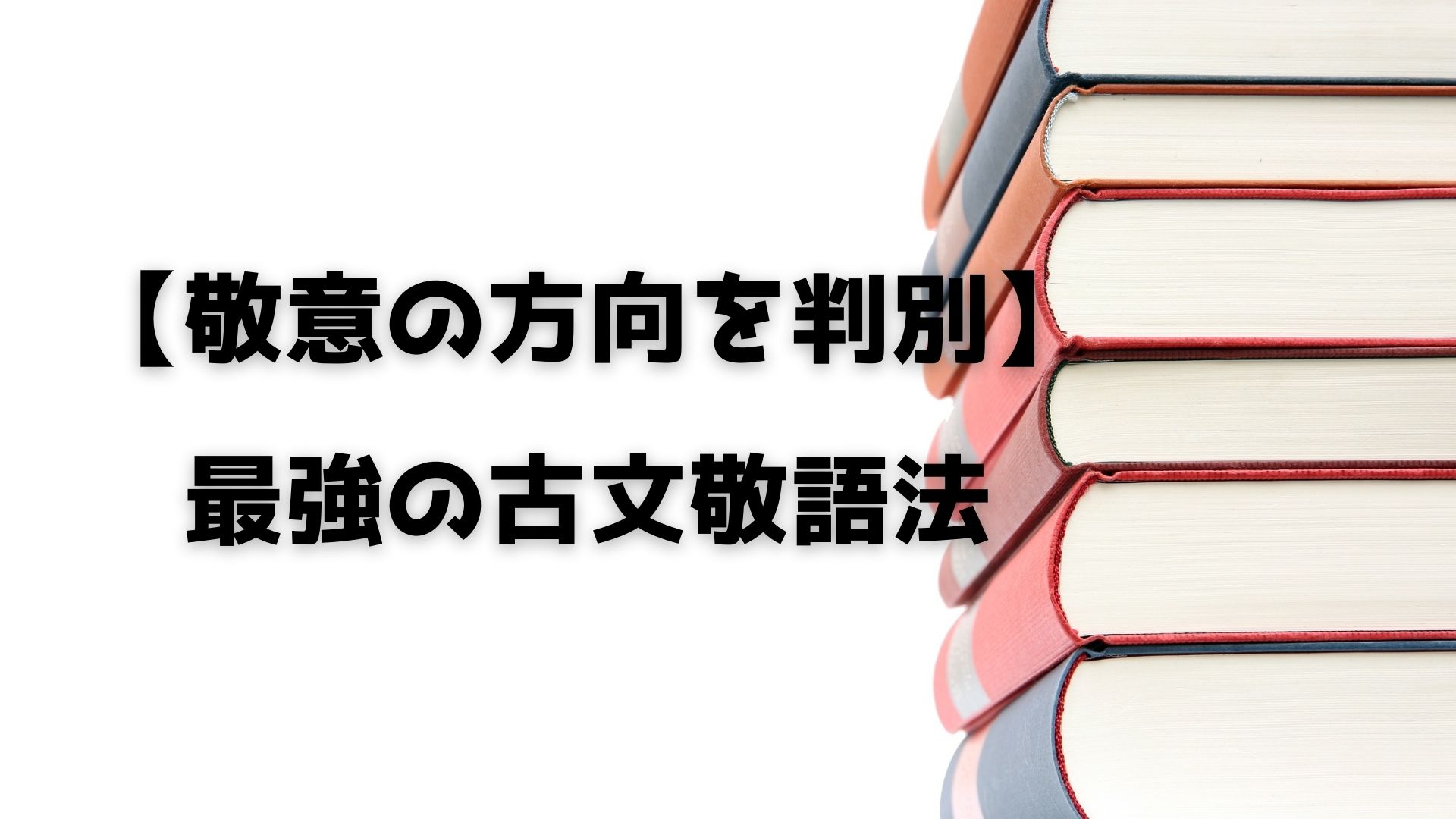広島大学文学部に合格するには?【受験のプロが入試傾向と対策を解説】

皆さんこんにちは。広大研講師の橋本です。
今日は広島大学文学部人文学科の合格を目指す人に向けて、
広島大学文学部人文学科の入試分析及び合格の為の具体的な受験戦略
について解説していきます。
この記事を読むことでわかることは
①広大文学部のここ数年の難易度
②合格するために何をするべきか
③実際に合格した広大研の生徒の勉強方法
です。
受験は体力戦でもあり情報戦でもあります。
必ずこのブログに書いていることをものにして受験を有利に進めましょう!
本記事の目次
広島大学文学部の特徴
広島大学の文学部は「哲学・思想文化学」「歴史学」「地理学・考古学」「欧米文学語学」などのコースがあり、かなり研究できることは多岐にわたります。広大生の中には「あそぶ(遊ぶ)ん学部」というふうに卑下する人もいますが、実際のところかなり自由が多い学部です。
自分の興味のあることに没頭できる最高の四年間を過ごせるのです。実際の文学部の学生にはユーモアセンスに溢れていたり、創造性豊かな企画力を持っている人が多く、かなり個性に溢れる人材が揃っています。
この自由な生活は就職にも大きく影響を与えており、教員や国家一般といった公務員になる人もいれば、トヨタ自動車などの製造業、銀行や生命保険といった金融保険業などに就職する人もいます。四年間の生活の中で自分の本当にしたいことを見つける人が多い印象です。
詳しい就職先実績についてはこちら!
広島大学文学部の入試入試科目と配点
実際に広島大学に受かりたいと思うのであれば、「どんな科目が出題されてどれだけの点数を取れば合格することができるのか」や、「自分と競争する相手がどれだけいて、最終ゴール点数はどうなるのか」を把握することが非常に重要です。特に文学部は広大の文系学部の中でも特徴的な配点をしているので必ずチェックしてください。
入試科目と配点
まずは、共通テストの科目と配点から見ていきましょう。
| 共通テスト | |
| 科目 | 配点 |
| 国語 | 200 |
| 英語 | 200 |
| 数学 | 200 |
| 理科 | 100 |
| 社会 | 400 |
| 情報 | 100 |
| 合計 | 1200 |
広大文学部の入試において一番鍵になるのが社会科目に400点配点されていることです。文系の王道科目である国語英語2つを合わせたのと同じ点数配分をもらっています。この社会で最低でも8割、できることなら9割以上の点数を取ることができなければ、受験を有利に進めることは難しいです。
また、数学には200点の配点があるものの、実は文学部生の多くが数学を苦手としています。人によっては90/200と半分以下の得点でも合格することがあるので、数学についてはそこまでケアする必要はないです。もちろんできるに越したことはないのですが。
国語、英語、社会、3科目のクオリティをどこまで上げられるかが文学部の合否を大きく分けます。特に先ほども言ったように社会にはたくさん時間を使いましょう。
次に個別学力試験の配点についても確認しておきましょう。
| 個別学力試験 | |
| 国語 | 400 |
| 英語 | 400 |
| 合計 | 800 |
広大文学部の二次試験の問題は国語と英語のみです。国語については「現代文、古文、漢文」の3問構成、英語については「英文要約、長文、英作文×2」という構成になっています。先ほど共通テストで大きな点数が割かれていた社会を加えて、「国語、英語、社会」の3教科は共通テストで9割の得点を目指すようにしましょう。
二次試験の合格者得点率は50~60%ほどであり最高得点率も75~80%ほどになることが多いため、しっかり勉強すれば順当に点数が取れる試験です。地に足をつけて勉強するようにしましょう!
最後に全ての試験の配点を合計したものを確認しましょう。
| 科目 | 共通テスト | 二次試験 | 科目合計点 |
| 国語 | 200 | 400 | 600 |
| 英語 | 200 | 400 | 600 |
| 数学 | 200 | – | 200 |
| 社会 | 400 | – | 400 |
| 理科 | 100 | – | 100 |
| 情報 | 100 | – | 100 |
| 合計 | 1200 | 800 | 2000 |
国語英語社会の配点はやはり高く、1600/2000を占めています。
高3の春まではこの3科目をがっつり勉強するようにしましょう!また2025年度入試から新たに情報が共通テスト科目に加わったことにより、以前よりもさらに共通テストでの逃げ切りを考える人が増えてきています。もちろん、二次試験も全体の40%分の配点があるので油断はできませんが、今までよりも共通テストでの判定が合否につながりやすくなってきています。
結局、受験は「合計点勝負」なので、共通テストの点数が低くても二次試験で巻き返せれば十分合格の可能性はあります。マーク系の試験が得意という人でも(もちろん最低限得点すべきラインはありますが)、二次試験のような記述が苦手だという人には不利ですから、判定が良くても油断をせずに勉強しましょうね。
倍率・合格最低点
次に倍率及び合格最低点のデータですが、広島大学のHPに掲載されている入学者選抜結果情報から前期試験のデータを引用しています。
| 年 | 倍率 | 合格最低点 | 合格平均点 | 共通テスト平均点(合格者) |
| 2024 | 2.2 | 1231/1900(64.8%) | 1298.4/1900(68.3%) | 818.2(74.4%) |
| 2023 | 1.8 | 1217/1900(64.1%) | 1309.7/1900(68.9%) | 827.2/1100(75.2%) |
| 2022 | 1.7 | 1199/1900(63.1%) | 1280.5(67.4%) | 795.6/1100(72.3%) |
共通テストの合格平均点からも分かる所ですが、合格者の多くは800点前後(約72%)の点数は確保しています。
科目によって得手不得手があるとは思いますが、合計点で70%以上は得点できるように各科目得点することを念頭に置いておきましょう。その上で重要になるのが社会の得点率です。
社会が8割取れると、それだけで320点の点が取れ、この場合2025年度以降の情報を加えて400/600点(66.6%)の得点で済みます。
まして9割の得点ができれば360点スタートになりますから、360/600(60.0%)の得点ができれば達成できるわけです。
また、個別試験ですが年度によって差はあれど、合格者は最低でも400、多くの場合480点ほどの点数をとっています。共通テストと比較すると問題の難易度も上がりますから、いかに共通テストで良い点数を取れるかが重要になってくるわけです。
実際に、広島大学の二次試験科目である『国語』『英語』は共に高難易度を誇り、特に『英語』は2021年度入試から傾向が変化(後述)したこともあり、そちらに合わせた対策も必要となります。
全体として見た時に、得点率70%以上を達成できていれば合格できると考えてください。
ここから、① 共通テストの得点 ② 二次試験の得点 をそれぞれどのように取っていくのかを逆算してもらえればと思います。
ここで一点注意してもらいたいことがあります。例えば、
「 ① 共通テストで60% ② 二次試験で80% を取ろう! 」のように二次試験に高得点を期待するのは現実的ではないということです。
前述した通り、広島大学の二次試験はかなり高難易度です。二次試験の合格者平均が60%程度であることからも分かる通り、ここで高得点を取るのは至難の業です。
そのため、基本的には共通テストでできるだけ高得点を取って、安心して二次試験を受験できる態勢を整えておくことを強く推奨しておきます。
ボーダーから40点ほど低い程度であれば全然二次試験でも勝負できるのですが、80点以上離れる場合には別の大学や学部を受験することをお勧めします。もちろんその得点層からの逆転合格を達成した生徒も生徒も広大研にはいますが、多くの場合もともと国語と英語の記述が得意な生徒です。
受験戦略
広島大学文学部を受験する上で肝となるのが、①全体で600点ずつの配点がある「英語」「国語」、②共通テストで点数配分の高い「社会」です。
この2点の対策なくして広大文学部への合格はありません。
ここからは、その重要な科目である『国語』『英語』及び『社会科』の学習について解説していきます。
具体的な勉強の内容やペースについて悩んでいる人は参考にしてください。
社会
まず、社会科の科目選択についてですが、こちらは基本的には何を選んでも良い(公民の2科目選択は不可)と思います。自分が勉強しやすいと思う科目を選んでください。※2025年度入試から歴史科目は「歴史総合」という科目が25点分配点されているので注意してください。
春から秋までに行うこと
地歴については、学校で習う範囲と合わせて「復習ベースで」勉強してください。余裕がある人は「予習」をすることをお勧めします。You Tubeなどを通して物事の大まかな流れを把握したり、参考書の太字の語句だけでも調べておくとかなり理解しやすくなります。
高1・高2で既習の範囲があって、そちらの内容が疎かになっている人は予習より先に、そちらの復習を行ってください。
基本は学校の教科書や資料集「共通テストの点数が面白いほど取れる本(黄色本)」、授業プリント等で暗記を行い、合わせて市販の「マーク式問題集」等で学習範囲の問題演習を行ってください。これを秋頃までひたすら続けます。
目安としては、最低でも10週は教科書や資料集などを読むようにしてください。覚えているかどうかの確認をしたい場合は学校の問題集を解き直したり、「ちとにとせ」というサイトで確認することをお勧めします。
公民科目も同様ですが、こちらは地歴と比べて範囲が狭いので早めに先取り学習をすることができます。参考書がそもそも少ないですが、「共通テストの点数が面白いほど取れる本(黄色本)」を読み込むことをお勧めします。公共についてはそんなに対策をすることがありませんが、教科書内容の復習だけはバッチリと行なっておきましょう。
秋から行うこと
地歴は学校のペースで学習をしていると未習範囲がまだ残っているとは思いますが、この頃から総合演習も行いましょう。
共通テストの地歴(特に日本史・世界史)は単純暗記だけでなく、与えられた資料を基に解答していく設問も出題されるため総合演習等で実際の試験形式に慣らしておきましょう。
当然、未だ学習してない部分もあると思うので、そこについては「へえ~そうなんだ」くらいで構いません。逆に、既習範囲の問題は確実に得点できるようにしておきましょう。
また、習っている範囲については絶対に3回以上は問題集の復習をしてください。間違った問題にはあなたが成長するために必要な知識がぎっしり詰まっています。3回以上復習してなお90点以上の点数が取れていないのであれば、取れるまで復習を続けることをお勧めします。
これを共通テスト本番まで続けてください。
地歴が上記ペースで進んでいれば、暗記範囲も終盤に近付き多少時間に余裕が出て来るので、ここで公民科目の勉強に本腰入れて取り掛かります。
まずは基礎的な知識詰めを約1ヶ月から1.5ヶ月で終わらせましょう。10月中に終わると理想的ですね。
社会科は演習量がモノを言います(何も考えずにただ解けばいいって話では無いからね)。もちろん、せっかく覚えたのに全て忘れてしまっては意味がありませんから、復習も必ず行うようにしてください。
「基礎知識詰め+範囲・分野別演習」→「総合演習」の流れを意識して年間の勉強計画を立ててください。
国語
広島大学文学部の国語は、「第一問:評論文」「第二問:古文」「第三問:漢文」を120分で解く記述形式の試験となっています。
共通テストが全てマークであることを考えると、出題形式が全く異なるのできちんとそれぞれに対応できるようにしておく必要があります。
春にすること
現代文は記述形式での学習を主に行います。
マーク形式の問題でも記述形式の問題でも、文章の読み方や考え方は変わりません。マークであっても記述であっても、大切なのは「自分なりの解答を作る」ことです。
文章を読み、設問に目を通して後、自分なりに解答を作る作業がマーク・記述共に超絶怒涛に大切なので、この訓練は早い段階から積んでおきましょう。
僕のオススメは、『入試現代文のアクセス 基本編(河合出版)』です。続編として『発展編』もありますが、記述現代文が苦手だという人は、まずは『基本編』から練習を始めていきましょう。
この教材で大事なことは、問題を解くこと以上に「解説を読み込むこと」です。解説というのは基本的に国語が大得意な人の脳内思考がそのまま現れているものです。その正しい思考の流れや論理を把握することは、一人でただ文を読むだけでは決して身につきません。可能なら解説を読んだ後に、もう一度文章を読んで自分の回答を作ってみましょう。
古文・漢文については、基礎的な古文単語や古文助動詞の識別、漢文の句法が頭に入ってない人はそこを最優先してください。
古文単語帳は個人が使いやすいもので構いませんし、助動詞やその識別の練習がしたいのであれば『ステップアップノート』等を使うことをオススメします。漢文句法も『ヤマのヤマ』や『漢文句法基礎ドリル』等で詰め込んでください。
いずれにしても、春の間に1周は必ず終わらせて、夏休みに入る前には復習を必ずしましょう。この基礎ができていなければ、これから先の勉強に進んでも効果が半減してしまいます。
上記に問題ないの人は、『古文上達』『マーク式基礎問題集』等で読解演習を行いましょう。その演習の中で、単語や句法に抜けがあればその都度確認をしてください。
夏にすること
現代文は変わらず記述形式での演習を続けてください。
『アクセス』を続けるでも良いですし、『得点奪取』等で少しステップアップした演習問題を行うでも良いと思います。どちらも問題ないという人は「上級現代文1」を購入して進めても良いでしょう。解説や回答の基準を丁寧に書いてくれている良問題集です。広大研の国語の一斉授業はこの問題集をベースに作成されています。
古文・漢文も『得点奪取』等でそれぞれ記述問題の演習を重点的に行うことを推奨します。特に現代語訳の問題には積極的に取り組むようにしましょう。
夏休みの終わり前には必ず今までの復習をしてください。
秋にすること
秋からは現代文・古文・漢文全てにおいて、『共通テスト』『センター試験』の過去問を解いていきましょう。特に、センター試験の問題は共通テストと比較してシンプルであり、単純な国語の実力を図るにはもってこいの問題になっています。解説についてはセンター試験の参考書を購入すれば確認することが可能です。
共通テスト形式については学校で演習している部分もあるかと思いますが、きちんと「時間を測って」通しで演習をしていきましょう。現在の国語の共通テストは、実力以上に情報処理能力や時間の使い方が大事な試験になっています。自分にベストな時間の使い方を必ず習得しましょう。
この秋から共通テスト本番までの期間でマーク形式の演習をたくさん積んで、時間や形式に慣れていってください。
共通テスト後にすること
「上級現代文1」または「アクセスの赤色」の評論の部分を5大問は解いてから赤本対策に移りましょう。
赤本の解説は非常に粗末なもので、どのように考えるべきかという思考がかなり薄くなっています。そもそもどう考えれば良いかわからない場合は、上級現代文やアクセスを必ず経由してください。
なお、広大の古文漢文についてはかなり優しい問題が多いです。わからないという場合は基礎知識が抜けていることが大半なので、必ず復習をするようにしてください。
後はひたすら過去問演習です。最低でも10年分は行ってください。
過去問を10年分位やった後は、広大オープンの過去問などでさらに演習を積みましょう。
英語
英語も国語同様に、文学部合格の要です。
まず、共通テストですが、2025年度から新しい形式に変化しています。これまで以上に英語の文章量が増えており文法や語法の問題はほとんどありません。しかし、正確な意味を取るための最低限の文法語法を身につけなければいけません。「ある程度正確な日本語訳」と「英語を素早く読む力」を図る入試になっているので気をつけてください。「入門英文問題精講」を完璧にしておけば文構造などで困ることはほとんどなくなるでしょう。この教材は音声があるので、発音しながら大まかな意味が取れるようになるまで繰り返し学習しましょう。
また、冒頭でも述べた通り、広大の英語は2021年度入試から傾向が変化しました。
「要約」問題については、「文章全体の要約」 → 「段落ごとに要約」
「長文」問題については、「超長文(文章を複合して1題として出題)」となっています。
年間通して心がけてほしいことが、英単語は「毎日」繰り返し学習することです。
特に単語帳の指定はしませんが、「速読英単語」や「キクタンリーディング」を併用することを強くお勧めします。
単語だけでなくその単語を使った文章がテーマごとに載っていて、単語の語法も勉強することができます。
また、どちらの教材もQRコードや専用の音声アプリを使ってリスニング教材としても使用できるので、1年かけて速単なら『中学編』『応用編』、キクタンなら『Basic』『Advanced』の2冊をマスターしましょう。できることなら文章をしゃべるところまで行うと一気に英語の処理能力が上がりますよ!
春にすること
まずは、英文を読んでいくための下地づくりをしましょう。
英文の構造を丁寧に把握する、いわゆる「英文解釈」と呼ばれるものです。
英文解釈系の参考書は多くありますが、オススメとしては『基本はここだ』です。この英文解釈を4月~6月で完璧にしましょう。同じタイミングで「速単中学編」の学習を進めることをお勧めします。
自分でSVを振り分けての文型把握をしたり、文中における修飾関係などが理解できるようになれば第一段階はクリアです。速単中学編については必ず音声を聞いて発音をするようにしてください。
その後は「入門英文問題精講」を1冊完璧にしましょう。
また解釈と同程度、またはそれ以上に単語を覚えることが重要です。広大にいきたいのであれば、夏前には単語テストで85%以上は点数を取れるようにしましょう!平日は毎日40単語、週末にその週に進んだ200単語の復習をすれば、2ヶ月半で単語は完璧にできます。毎日コツコツ頑張ることが何よりも大事です。
夏にすること
夏期はかなりハードです。
まず二次試験対策として「英作文」の練習を行います。
『英作文のトレーニング』等で英作文の基本的な書き方や、英語における自然な表現を覚えていきましょう。
また、英文解釈も一段落ついていると思うので、ここからは長文読解も併行して行います。
長文については1日1長文は読むことを心がけましょう。
その際に、春にやった英文解釈の知識等を意識しながらできると良いですね。
この頃から「速単必修編」を進めることも大事です。素早く読む能力が秋以降に求められますから、音読を行って処理スピードをどんどん上げていきましょう!
秋にすること
秋からは共通テストの過去問等を使って演習を行いましょう。共通テストのリーディングは時間がかなりシビアです。特に2025年度から分量がさらに増加しています。文章の深い理解というよりも、そこそこの情報を整理しつつ選択肢を処理することが求められますから、たくさん問題を解いてみましょう!
制限時間いっぱい集中して問題を解き切る体力をつけるという意味でも、過去問演習を可能であれば1日1年分は解きましょう。また、重要な単語やフレーズは必ずメモ帳に残すようにしましょう。知識は自分で使いこなせるようにならないと意味がありませんよ。
共通テスト後にすること
要約問題はかなり日本語訳の力が求められます。入門英文問題精講などを解き直して訳の確認を行ってからスタートしましょう。単語も共通テストレベルからさらに難しくなっています。シス単やターゲットといった単語帳を完璧にしておくことも忘れずに。
英作文についてもフレーズの復習は最低限行ってから進めましょう。
国語と同様にひたすら過去問演習を行いましょう。
10年分は解き切ったら、オープン模試等でさらに演習を重ねてください。
特に要約も英作もここ最近で大きく傾向が変わっていますから、今と同じ形式でときたいのであればオープン模試の問題を強くお勧めします。要約については「ディスコースマーカー英文読解」を並行して進めることをお勧めします。
また『要約問題』『英作文』は学校や塾の先生に必ず添削をしてもらい、自分がどの程度解けているのか点数化してもらうようにしましょう。
理数や情報
上の3科目と比較すると配点は低いものの、点数を取る上で他教科を蔑ろにするべきではありません。特に理科と情報についてはかなりコスパが良いので、紹介しておきます。
まず、理科については学校のワークを進めることを最優先にしましょう。
その上で「基礎問題精講」シリーズを解き進めたり、マーク問題集を進めることをお勧めします。単純な知識の確認をしたいのであれば、センター試験の過去問を解き進めると良いでしょう。
目安としては3年生の秋口から着手すればかなり早い方です。2つの科目を同時に進めるのではなく、片方ずつ完璧にするように心がけましょう。必ず2週間に1度は復習を挟むようにしてください。
情報については、資料読解問題や知識問題、プログラミング問題などがバランスよく散りばめられています。広大では2025年度入試で100点の配点が振られていました。これは他大学と比較しても高く、他の大学の多くは50点の配点しかないことを考えると、広大に入る上では情報を詰めることはかなり大事です。
参考書が少ないですが、一冊自分の好きなものを完璧にするように心がけましょう。
プログラミングについても、学校の問題集+1冊は必ず進めてください。
広大研では、季節講習として情報の授業を行なっているので、興味のある方はぜひ申し込んでみてくださいね!夏休み前後から情報に取り掛かることをお勧めします!
まとめ
長々と話してしましましたが、いかがだったでしょうか。
広大文学部を目指すのであれば春の内から基礎を固め、二次試験レベルの記述力を養成していくことが必要不可欠です。
また今回取り上げた学習ペースや参考書はあくまで成功の一例です。これが全てというわけではありません。
人によって参考書の適不適がありますし、ペース及び理解度だってそれぞれだと思います。
大切な事は、『自分に合ったペースで』『正しく努力する』ことです。
愚直に努力することは美徳ではありません。
自分の時間を無駄にしないためにも、きちんと計画を立て、常に最適を考えながら学習する習慣を付けましょう。
「広大研」は広島の高校生の第一志望合格をサポートしています

当サイトを運営している広大研は、「受験にドラマを」を合言葉に、第一志望に合格したい!という広島のみなさんを徹底サポートしています!
広島大学だけではなく、旧帝大・難関私立への合格実績も十分です。
予備校を探している広島の高校生は、以下記事をぜひお読みください!
- 広大研のリアルな感想・評判を卒業生にインタビューしてみた!
- 広島の予備校「広大研」への入塾をオススメする受験生の特徴とは!?
- 医学部医学科を受験される方は以下の記事をご覧ください。
広島大学医学部医学科に合格するには?【プロが傾向と対策を解説】