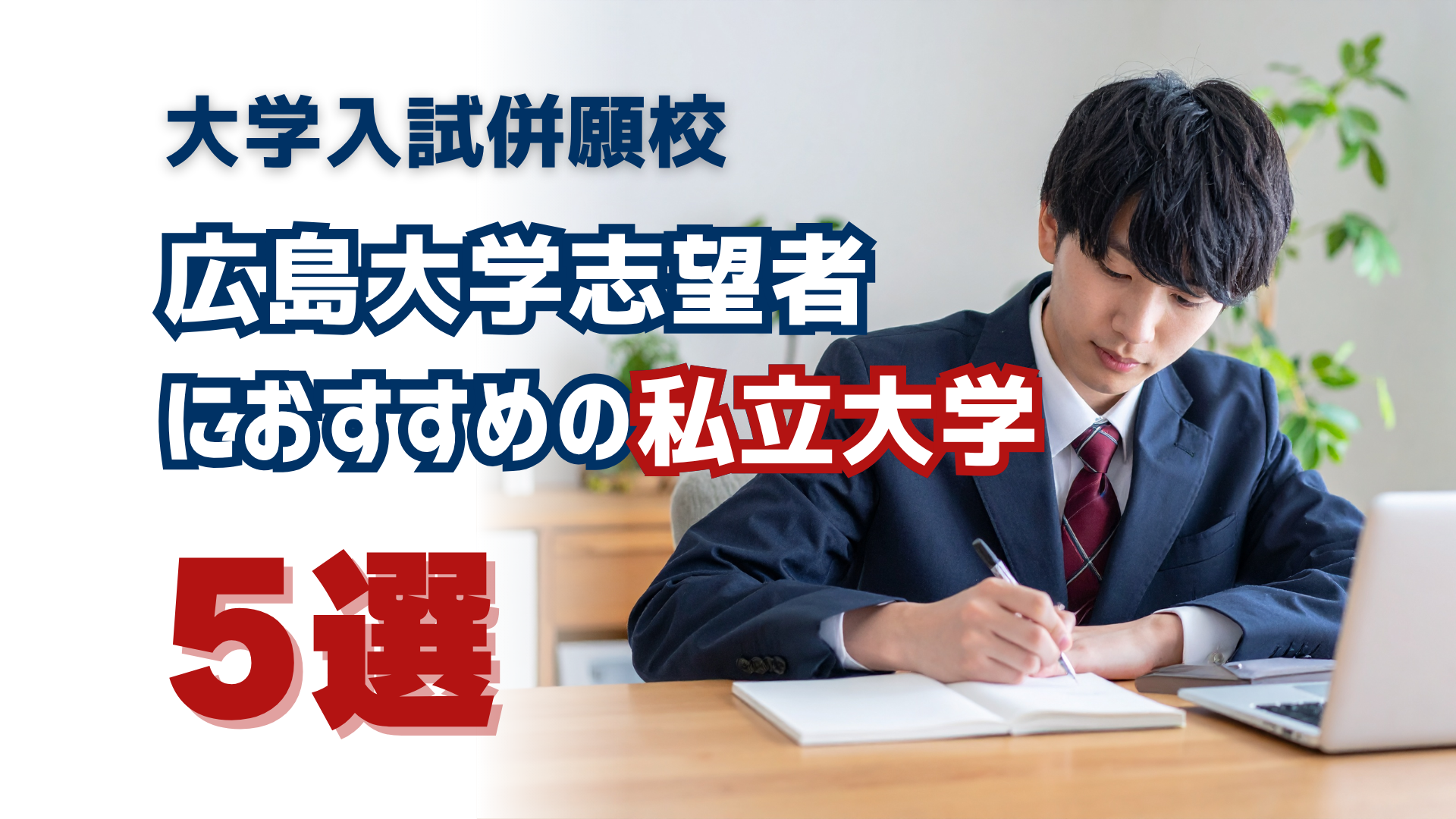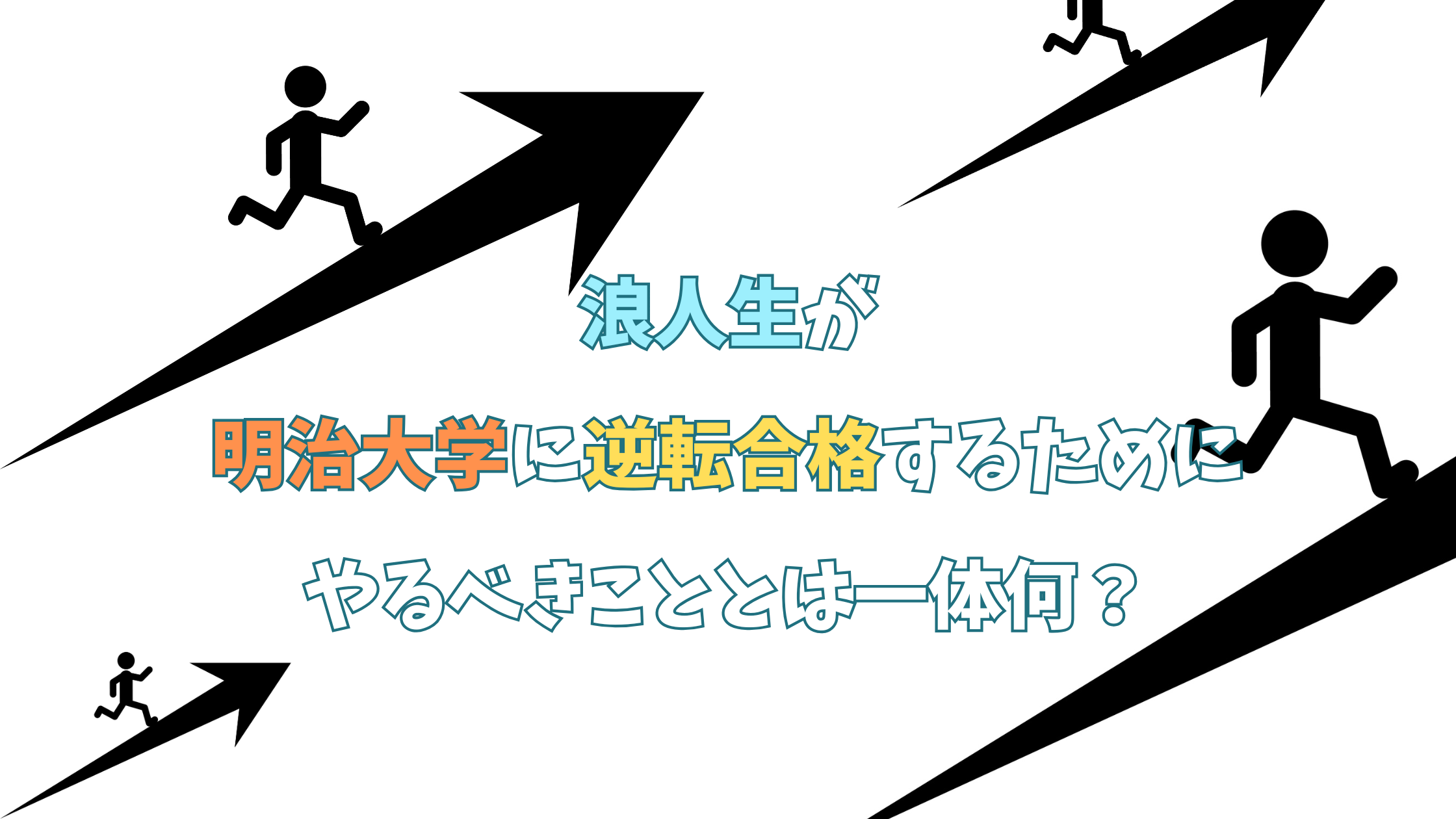【傾向と対策】広島大学総合科学部総合科学科(文系受験)に合格するには?【プロが解説】

こんにちは。広大研公式ブログ編集部の中野です!
「広島大学総合科学部総合科学科に合格したい!」
という方がこの記事を見ていると思うのですが、総合科学部文系受験の「特殊な配点」であったり「小論文対策」であったりが不安ではありませんか?
この記事では、広島大学総合科学部(文系受験)に合格するために必要な情報を、入試制度の特徴から具体的な勉強法、科目別の対策方法まで詳しく解説します!
1. 広島大学総合科学部の特徴
2. 受験戦略
3. 受験計画
という3ステップで解説していきます。
受験生だけでなく保護者の方にも役立つ内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。
本記事の目次
広島大学総合科学部(文系受験)の特徴
それでは初めに、総合科学部総合科学科の特徴について確認していきましょう。
何よりも一番に紹介したいのが、学科の分け目なく幅広い分野の学びを自由に選べるということです。
総合科学部の学部等は他の学部と比較してもかなり大きく、教授の授業内容もかなり多岐にわたっています。
その中から自分の一番興味のある分野を見つけて、研究を進めることができるのです。
また、分野ごとに分けられがちな研究を横断して総合的な研究をすることもできます。
例えば、自然科学と人文科学、社会科学は切り離されることが多いのですが、総合科学部であれば文理の混ざったこの分野を総合的に学習および研究できるのです。
さらに就職についても幅がかなり広く、公務員や一般企業就職だけでなく、NGOなどに就職する方もいます。
「やりたいことが決まっていない」という高校生の方にはうってつけの学部と言えるでしょう。
友人関係についても文理問わず多くの人が総合科学部には集まりますから、大学生活の中で刺激をもらって自分の人生の方針が決まることもありますよ!
広島大学総合科学部の入試科目と配点(文系受験)
総合科学部の文系受験は広大の中でもかなりクセのある入試ですから、下の内容を読み込んで自分だけの戦略と勉強法を見つけましょう!
なお、今回この記事では、前期試験について書いていきます。
また、国際共創学科(IGS)についても省略させていただきますので、あらかじめご容赦ください。
総合科学部(文系受験)
それでは入試科目と配点について確認してみましょう。 →令和8年度入学者選抜に関する要項
| 英語 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 情報 | 小論文 | 合計 | |
| 共通テスト | 200(★) | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 1000 | |
| 2次試験 | 600 | 600 | 1200 | |||||
| 合計 | 800 | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 600 | 2200 |
★英検やTOEIC、TOEFLなどの利用によって満点扱いになることもあります。
広島大学総合科学部で文系受験をする場合その最大の特徴は
2次試験に数学がなく小論文が存在する文系重視の配点であることです。
特に小論文について詳しくは後述しますが、
5つの資料を読み取り、そのうちの3つを用いて3時間内に1200字の論文を書くことが求められます。
2次試験の配点を見てみると、英語600点と小論文600点の 合計1200点となっています。
共通テストも合わせて考えてみると、
共通テストと2次試験の合計得点の2200点中、 英語が800点 、小論文が600点
合計1400/2200(63%)を占めています。
このように配点からもわかるように文系重視の 入試となっています。
広島大学総合科学部に合格するための受験戦略と勉強法
ここまで入試配点を確認してきて、英語と小論文(国語)を重点的に勉強するべきだということはわかったと思いますが、実際に何点の得点があれば広島大学に合格できるのでしょうか?
昨年から導入された情報の影響もありボーダーは不安定になっています。
今回は過去のデータを参考にしながら、大まかなボーダーラインを紹介します。
①行きたい学部の合格最低点を把握
まずは過去の入試結果を確認してみましょう。→入学者選抜結果情報
合格者の情報を見てみます。こちらは前期試験の情報になります。
| 総合点 | 大学入試共通テスト | 個別学力検査(2次試験) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配点 | 最高 | 平均 | 最低 | 配点 | 最高 | 平均 | 最低 | 配点 | 最高 | 平均 | 最低 | ||
| 2025 | 文科系 | 2200 | 1775 | 1599.3 | 1525 | 1000 | 834 | 750.1 | 679 | 1200 | 957 | 849.1 | 768 |
| 理科系 | 2200 | 1659 | 1389.4 | 1208 | 1000 | 834 | 730.9 | 586 | 1200 | 894 | 658.6 | 512 | |
| 2024 | 文科系 | 2100 | 1670 | 1452.5 | 1372 | 900 | 754 | 646.9 | 589 | 1200 | 957 | 805.7 | 726 |
| 理科系 | 2100 | 1536 | 1253.9 | 1106 | 900 | 755 | 640.4 | 550 | 1200 | 898 | 613.5 | 452 | |
| 2023 | 文科系 | 2100 | 1557 | 1429.0 | 1340 | 900 | 726 | 652.8 | 582 | 1200 | 918 | 776.3 | 645 |
| 理科系 | 2100 | 1655 | 1374 | 1265 | 900 | 723 | 639.9 | 547 | 1200 | 948 | 734.1 | 640 | |
皆さんもこのようなグラフを見たことがあるかもしれませんが、大事なのは「総合得点の合格最低点」です。
共通テストや二次試験単体の点数を確認してもあまり意味はありません。
合格者の最低点を見ていくと 、文系受験では大体1550点(総合得点の70%)あたりをとると、十分合格圏内だということがわかりますね。
2025年度の試験から情報が加わったこともあり全体として合格ラインは不安定ですが、全体点1550を目指すのがひとまずの目標となるでしょう。
ただし、「みんな7割くらい点を取れるから自分も取れるだろう」といった油断はしてはいけません。
実際に共通テストと二次試験の過去問を解くと感じると思いますが、得点率7割は決して簡単なことではないです。
②「模試」と「過去問」を利用して現在の学力状況を知る
高校3年生になるとマーク模試や記述模試といった外部模試の回数が増えます。
その中で、自分のわからない部分を分析し今後の勉強に活かしていくことは非常に重要です。
合格者の同時期の共通テスト得点率を確認して相対的に自分の位置を測ることもできますし、単純に判定を通して自分を相対化できます。
勉強をする中でこの相対化がないとモチベーションの低下を起こしかねませんから、外部模試は積極的に受けるようにしましょう。
特に11月に実施される「広大オープン」については他の予定よりも優先するべきです。
広島大学の二次試験と同じ形式で、同じ広大を受ける人たちの中での順位がわかります。小論文の模試はただでさえ少ないですから、必ずチャレンジしましょうね。
過去問については、大学側が採点基準を明確にしていないため数値化は難しいでしょうが、形式に慣れておくことと解く中で自分が次に何を勉強すればもっと解けるようになるかがはっきりします。
「受験は過去問に始まり過去問に終わる」というくらい過去問は大事ですから、共通テストが終わるまで後回しにすることは絶対にやめましょう!
広島大学総合科学部(文系受験)へ合格するための科目別対策

それでは次に受験計画についてお話ししていきます。
各科目それぞれについて どのように勉強していけばよいか、個別にポイントを確認していきましょう。
英語対策でするべきこと
広島大学の英語は同レベルの他大学と比較してもかなり難しいです。
どの大問も特徴があり、第1問の英文要約問題、第2問の長文読解は関連する2つの文章を比較しつつ読み進めるという珍しい形式で、第3、4問の英作文はデータやグラフを説明する問題とテーマ英作文になっています。
共通テストの対策はもちろんしなければならないのですが、共通テストに苦しんでいると二次試験の英語はかなり厳しい勝負になってしまいます。
意識配分としては、二次試験対策をしている最中に共通テストの読解に必要な解釈読解力をつけて、12月1月に調整で一気にマーク参考書を解き進めて共通テストに臨むようにしましょう。
各大問の対策については以下の通りです。
第一問の対策として「入門英文問題精講」や「英文解釈の技術100」などの英文解釈系の参考書を1〜2冊、第2問の対策として「やっておきたい英語長文500および700」などの長文読解問題集を2冊〜3冊、英作文対策として「基礎英作文問題精講」などの参考書を最低でも1冊進めておきたいところです。
共通テストとの兼ね合いを考えると、解釈と長文読解は優先して行いたいところです。
自由英作文についてはフレーズのストックと英検2級の英作文を解いておくことをおすすめします。
春にすること
まずは単語と文法を最低限学習定着させましょう。ここが疎かだと全く内容が定着しなくなります。
地道ではありますが、じっくり進めていきましょう!
単語帳はシス単やターゲット1900、キクタンの6000などであれば問題ないでしょう。必ず単語を覚える時は発音をしながら覚えるようにしてください。
国語でも、熟語の意味はわかるのに読み方がわからないというのは不自然ですからね。正しい知識体系を作る上で発音は大事です。
文法についてはポラリス1や高校で扱っていた問題集で大丈夫です。文法問題を解くための勉強ではなく、あくまで解釈を進める上で必要な文法的知識を抑えることが目標ですから、目的を間違えないようにしましょう。
ここまで完璧な方は夏のステップを先取りしてもらいます!
夏にすること
夏は二次試験に向けて一気にレベルアップを図る時期です。速読英単語の必修編を進めつつ、入門英文問題精講を完成させる。
2周目からは音読しつつ文の構造を把握し、大まかな日本語訳を作れるようにしておきましょう。
英語長文については500語程度のものまではチャレンジして良いです。難しいという人は300単語程度の参考書から進めると良いでしょう!
夏休みには必ず復習を行い、得られる知識はすべて定着させておきましょう。
余裕がある方はぐんぐん伸びる英語長文シリーズのstandardを進めるのも良いでしょう。
秋にすること
秋は本格的に広島大学の過去問を解いていきましょう。実力にはまだギャップがあると思いますが、入試の形式と自分に足りない力を確認することが大事です。
過去問の目安は3〜5年分とします。英作文については、このタイミングで「基礎英作文問題精講」を進めるのが良いでしょう。
実力が足りない場合は上述したぐんぐん伸びる英語長文シリーズ(advance以外)を進めるようにしましょう!
余裕がある方はやっておきたい英語長文の700まで進めましょう!
冬にすること
11月の2週目までは広大の過去問を進めても良いです。ただしその後は基本的に共通テストの演習を進めるようにしましょう。
二次試験に英語があるわけですから最低でも80点の得点を継続して取り続けることができるようになりましょう。理想は90点以上の点を取ることです。
リスニングについても共通テストの形式にカスタマイズしましょう。
なお、ここまでおすすめした教材は全て音声がついています。音声を聞き発音をすることによって、ある程度のリスニング能力はついているはずです。
小論文(国語)対策でするべきこと
この科目は広島大学の中でもかなり異質です。
5つの文章から3つを選択し、それについて要約した上で自分の意見を1200字程度で書く必要があります。
600字程度の通常の小論文と異なり、事前の準備をしっかりとしないと太刀打ちできません。
必要な能力は
①単純な読解力
②発想力およびそれにつながるような経験(実体験でも本による知識でも可)
③小論文の考え方書き方についての知識
の3つに分かれると考えてください。
①については、文章月の小論文を解く際に毎回要約を進めておけば安定してきます。必ず解説を確認して自分の考えと本文の内容に齟齬がないかの確認をするようにしましょう。
②についてはセンスだと考える方もいますが、いかに色々な本を読み(もしくは小論文を解き)色々なことを考えるかが大事です。その場のぽっと出の発想ももちろん悪くありませんが、他の文章や小論文で書いたことがある内容の方がやはり安定しており、わかりやすくなります。「まるまる使える入試頻出課題小論文」などを受かって、色々なテーマに触れておくことをおすすめします。また文章量についても、文字数の指定を1200字にすれば広大を想定した演習をすることができます。
③について、受験生が面倒くさがりがちなのですが、小論文の理論書を読むことは非常に重要です。学校の先生や塾の先生に口頭で教えてもらうことも大事なのですが、やはり本を読んである程度自分の知識を確立した上でアドバイスを受けた方が吸収効率が高いです。夏休み前には1冊読んでおきましょう。
春にやること
春先はまだまだ小論文をやれる状態ではありません。他教科の勉強を進めつつ、小論文の理論書を1冊隙間時間に読むようにしましょう。大事なところや使えそうな部分はメモをとって見返せるようにしておくと良いです。
また、国語に関しては古文単語と「漢文早覚え即答法」を進めましょう。GW明けには完璧にできるように、優先的に進めておくと良いです。
夏にやること
「まるまる使える入試頻出課題小論文」などを用いて演習をスタートします。
解説を読み込むことと、自分の作った小論文の読み直しをすることを必ず行なってください。国語については、1週間で1年分センター試験の過去問を解いておくと良いでしょう。
秋にやること
参考書の字数を1000字に変更して2周目を解いてみましょう。それが終わったら、広島大学の過去問にチャレンジしてみましょう!
なお、11月以降は一旦共通テストに向けて国語を進めることをお勧めします。
冬にやること
共通テストが終わるまでは共通テストに集中です。終了後は理論書の読み直しと、参考書で2問演習を積んでから、広大の過去問をどんどん解いていきましょう!必ず、他の人に添削をもらうようにしてくださいね!
数学対策でするべきこと
数学については重要度は高くないものの200点分の配点があります。
各大問を(2)の途中まで解けるようになることが目標になるでしょう。
特にデータや微積分といった出方が固定されている大問を中心に対策することをお勧めします。
国語英語よりも時間をかけることはできませんが、情報や理科基礎よりも優先的に勉強を進めていきたいところです。
記述模試の数学については使う予定がないので無視して大丈夫です。
春から夏休みまでにすること
まずは黄色チャートや基礎問題精講などの問題集を軸に基礎固めを行いましょう。
難しい問題を解くことがゴールではないので、まずは簡単な問題を通して 公式一つ一つの意味を理解し、どのような場面で公式や定理を使えば良いのか適切に判断できるようになるための下準備を整えて おきましょう。
ここで手を抜かず丁寧に反復することが、後の勉強のスピードや効率をアップさせます。
自分の考えがあっているか不安な場合は、周りの友だちや信頼できる先生の力に頼りましょう。
また、数学が苦手な方は入門問題精講シリーズおよびYouTubeの解説動画を見てインプットしてから黄チャートなどに臨むのも良いと思います。
目安は一日40分〜1時間といったところになるでしょう。
夏休みににすること
夏休みはやってきた内容の中から、苦手単元を徹底的になくすことが目標です。
単元にとどまらず、計算が苦手であれば計算演習を学習計画に盛り込むことも大切です。
特に二次関数、三角関数、微積、確率、ベクトルあたりは優先的に進めておくと後々楽ですよ。
自分で絞った単元を最低でも2周、できるなら3周進めるようにしましょう。
秋にすること
夏休みに進めた単元に加えて、共通テスト演習を大問固定で進めていくと良いでしょう。例えば、大問1だけを6回分解く、といったように進めてみましょう。解説をしっかり読み、これまで学習してきた知識がどのように使われているのか、なぜその公式を使うのかをしっかり理解しましょう。
共通テストの演習が難しいようであれば、センター試験の過去問を解いてみてチェックするのも良いですね。
こちらも必ず解説を読み込んで解き直しをしておきましょう。
ちなみにこれ以降は共通テスト演習を進めていくだけです。時間を空けて今までといた問題を解き直すのも良いでしょう。
社会対策でするべきこと
社会については2科目を選択する必要があります。どちらも70点を目標に勉強すると良いでしょう。
特に公共政経は70点前後まではそこまで苦労しない科目ですから、まだ社会科目を選択していない人は公共政経を優先して選択すると良いでしょう。
夏休みまでにやること
学校内容の先取りもしくは今までの学習内容の総復習の2択ですが、歴史科目は先取りの方がメリットが大きいです。
近代以降は歴史総合とも関わりますし、大問として出やすい部分も多いです。
やり方としてはYouTubeで動画を見た後に、「面白いほどわかるシリーズ」などの参考書に書き込みをしつつ読み込み、その後「ちとにとせ」というサイトで知識のアウトプットを行います。
逆に地理に関しては今までの復習を学校のワークなどを通して進めることをお勧めします。
公共政経については公共分野を3年生になって扱うことはほぼないので、まずはそこの復習から始めましょう。その後、政治か経済の興味のある分野から進めていきましょう!こちらも「面白いほどわかるシリーズ」などの参考書をお勧めします。
夏休みの終わりまでに「各教科最低でも学校で進んでいる範囲までは1周復習が終わっていること」、歴史科目については「先取り学習が1周終わっていること」を目標としましょう。
秋にやること
社会を本格的に勉強するのは秋になってからです。もう1周内容を復習しつつ、今度は該当する範囲のセンター試験や共通テストの過去問を解いてみましょう。
必ず解説を確認して、もし覚えていない部分があれば週右辺知識とセットで覚えるようにしましょう。もし点数が50点を超えていないようであれば、まだ基礎知識が足りない可能性が高いです。
学校のワークなどをもう一周まわすことをお勧めします。量をこなす以上に、何を覚えるかが大事です。
冬にやること
基本的に冬は共通テストの演習です。マーク参考書は4冊程度解くようにしましょう。
必ず復習をして次に時間をおいて解いても最低95点を取れることが良い復習の目安です。
直前期は今までといた問題が全部解けるのか確認すると良いですね。
理科基礎対策でするべきこと
理科基礎はその範囲と難易度の割に配点が高いコスパの良い科目です。
高2の段階で大体の高校は学習を終えていますから、3年生は授業内で演習を行うことになります。
演習をする中で、先生の解説がわからない場合は、教科書やワークの読み直しをすることをおすすめします。
逆に、解説の理解に苦労していない場合は、学校で行った演習の復習を行なっておけば大丈夫です。
最低でも70点を目標にしましょう。
7割の得点に向けて本腰を入れて勉強するのは3年生の11月からになります。
また、地学基礎はある程度まとまった点数が取れますが、計算問題を完璧にしないと高得点にはなりません。典型的な問題は解き込んでおくとお得です。
秋にすること
具体的には11月ごろから本格的に理科基礎の演習を進めていきましょう。
この時期から他の教科も演習に入るため、理科基礎に時間を取る余裕も出てきます。
計算問題は計算のやり方と理屈、知識問題については間違えた場合は周辺知識までセットで覚えるようにしましょう。
ノートなどを作って見返せるようにしておくと非常に良いですよ!
これ以降は基本的に演習と復習のループです。あまり時間を理科に偏らせすぎないように注意してくださいね!
情報対策でするべきこと
2025年度から新しく追加された情報ですが、知識とプログラミングの両方を理解することが求められます。
特にプログラミングについては理解に時間がかかりますから、参考書を使って早めに始めておくと良いでしょう。
また、広島大学では100点の配点がふられていますから、優先度としては社会と同等です。あまり後期まで放置しないようにしましょう。
目標は60〜70点になります。2025年度、2026年度の2回分のデータからある程度の平均点は決定されるでしょうが、絶対的な数値として60~70点を取ることを目標にするべきです。
また、広島大学は2026年度入試時点で情報の配点が圧縮されることがない珍しい大学です。
単純な知識を整理しておくことと、プログラミングを勉強しておくと安心ですよ!
秋までにすること
「決める!共通テスト情報」などの参考書を使って知識をある程度まとめておきましょう(最低2周)。
また、プログラミングの単元は参考書だけでなくYouTubeなどで動画を探し、重ねがけしながら学習することを強くお勧めします。
10月以降は共通テスト形式で演習しながら解説を読み込み、知識のノート化とプログラミングの解き直しを継続していきましょう!
全体的な受験戦略方針

それでは次に、全体的な受験戦略方針についてお話ししていきます。
文系受験においては、いかに国語と英語で高得点をとっていくかが合格できるかどうかの鍵となります。
次の表のように 共通テストと 2次試験の 配点を比較してみると二次試験の方が配点は大きくなっています。
| 英語 | 国語 | 数学 | 理科 | 社会 | 情報 | 小論文 | 合計 | |
| 共通テスト | 200(★) | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 1000 | |
| 2次試験 | 600 | 600 | 1200 | |||||
| 合計 | 800 | 200 | 200 | 100 | 200 | 100 | 600 | 2200 |
★英検やTOEIC、TOEFLなどの利用によって満点扱いになることもあります。
しかし、小論文という不確定要素がある以上、共通テストである程度の高得点を目指したいところです。具体的には750点の得点があれば安心できるでしょう。
また点数配分を見ると数学、理科といった理系科目の配分がやや低いことがわかります。
とはいえ全体点70%を目指す上で完全に見過ごすことができるものではなく、ある程度の点数は取るべきです。
具体的には数学は55%の得点率、理科に関しては70%の得点を取るべきです。
また二次試験で使う英語および国語(特に現代文)については9割以上の得点を取るべきです。
英検準1級をはじめとした英語資格を取得し二次試験の演習に備えるのも良いでしょうし、小論文では前提として文章理解と思考が必須になりますから、共通テストの現代文では95〜100/110点を取れるようになるまで鍛え上げましょう。
(※ 英検についての記事はこちらから!)
総合科学部の文系受験に焦点を絞った勉強をするのであれば 、英語や国語に時間を割きつつ、
数学は5.5割、理科基礎7割、社会や情報も7割は点を取り 、英語や国語の得点を 9割近くまで引き上げるために時間や労力を割くべきだと考えます。
また、共通テストの国語とは異なる能力を求められる小論文試験対策も、遅くとも3年生の夏からコツコツと進めていきましょう!
文系科目について
ただがむしゃらに勉強すればいいというわけでもありません。
文系教科の中でも特に英語と国語を勉強していく上で、意識しないといけない重要なことことがあります。
それは、演習ばかりになっていないかということです。
解けば上達する科目ではありますが、ある程度の知識は必要です。
英文和訳教材及び国語の読み方と解答の書き方の参考書、理論書を読み込むことを強くお勧めします。あまり意味がないように思えますが、何周も読み続けることと期間をあけて読み直すことによってその重要さに必ず気づけます。
また国語とは少し違いますが小論文についてはなおさら演習の前に理論書を読むべきです。
各分野についての背景知識や論理構成、発想などはオリジナルのものを生み出すことも大事です。ただ、基礎の上に生まれるオリジナルの発想思想の方が必ず質は良くなります。
学校などで行われる小論文指導を受ける前に理論書を最低1冊、できれば2冊は熟読するようにしましょう。
理系科目について
試験の配点からもわかるように、理系科目は労力や時間に対して得られる得点が多くないので、効率よく要点を絞った勉強が重要になってきます。
出題内容から、配点が高い分野や得点しやすい部分から優先的に勉強していくのが良いでしょう。
目標の得点としては、6割くらいを目安に取れれば妥当でしょう。
広島大学総合科学部合格のために今すぐするべきこと
ここまでさまざまな受験戦略についてお話ししてきましたが、では今すぐに学生の皆さんが総合科学部合格のためにできることはあるのでしょうか?
主に3つあります。
1つ目は、共通テストの過去問を解いてみて自分の現状の得点力を確認することです。
この記事でお伝えしたように合計で750点が取れていれば安心できるでしょう。
もし不足しているのであれば、不足している科目の勉強に取り掛かるべきです。
2つ目は、小論文の参考書を読み込むことです。基礎的な構成や考え方を定着させることが重要だとお話ししました。
がむしゃらに解くよりも、理論書を読んだり時間がないならYouTubeを見て、何をすれば良い小論文になるのかを知っておきましょう。
その後は600字程度の小論文に挑戦してみましょう!
3つ目は1つ目と内容が被るのですが、基礎知識の総復習です。
共通テストの過去問で600/1000点程度の点が取れている人は演習を進めても良いのですが、それ以下の人はそもそも知識が足りていない可能性が高いです。
学校のワークや参考書のレベルから一気に振り返りをするべきです。
以上を行いつつ、「長期的に自分は何をする」という計画を紙に書き出してみましょう!困った時には広大研に相談ください!
広大研では無料の体験授業を実施しています

今回は、総合科学部総合科学科の文系受験について、入試の傾向とその対策についてお話しさせていただきました。
この記事を読んでどのように勉強すれば良いか明確になってもらえれば嬉しいです。
「なんとなく何をすれば良いかはわかったけど、具体的にどうすれば良いのかわからない」という場合には、いつでも広大研までご相談ください。
また、広大研に少しでも興味を持ってくださった方や、「逆転合格で第一志望合格を狙いたい!」という方も、まずは気軽に無料体験授業にお越しください!
さらに、こちらから無料体験授業に申し込んでくださった人は、入塾金1000円OFFのキャンペーンも開催中です!
以下の記事では、広大研と相性の良い生徒の特徴を解説しています!
【参考記事】
- 広島の予備校「広大研」への入塾をオススメする受験生の特徴とは!?
- 英検準1級を取ると広島大学の入試は有利なの? プロ講師が解説!
- 広島大学情報科学部情報科学科に合格するには
- 広島大学に逆転合格できる?D・E判定は厳しいのか?