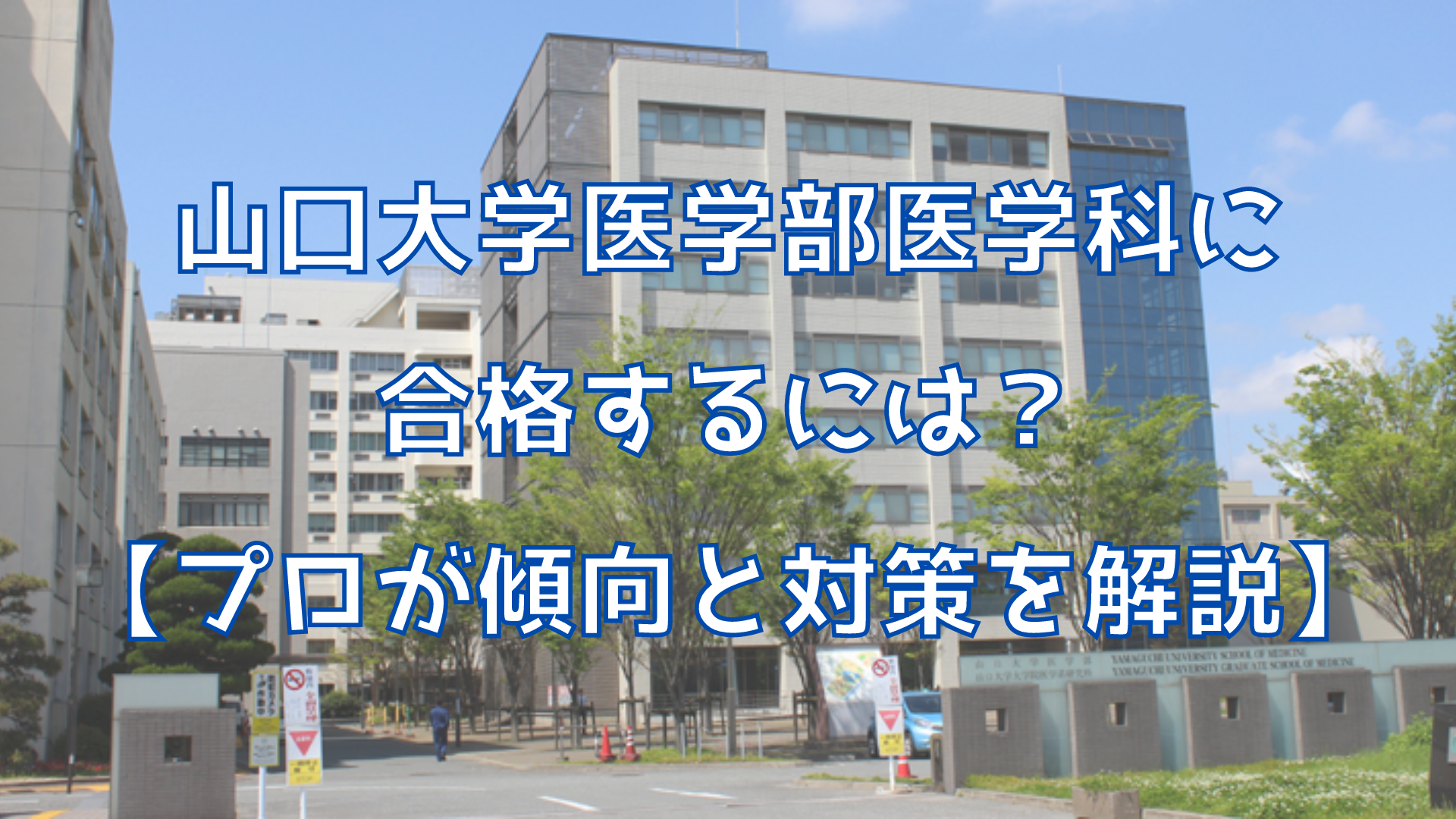岡山大学医学部医学科に合格するには?【プロが傾向と対策を解説】

岡山大学医学部医学科に合格するには?【プロが傾向と対策を解説】
こんにちは!
広大研公式ブログ編集部の川口です。
今回は医師を目指して岡山大学医学部医学科への合格を狙うあなたに向けて、
岡山大学医学部医学科の入試結果分析を行い、そこから合格に向けた受験戦略と受験計画
について書いていこうと思います。
もしかすると、あなたは
「広大研いうレベルも低そうな小さい塾の情報なんて信用出来ねー」
と思っていらっしゃるかもしれません。
しかし、もちろん私は医学部医学科出身ですし、広大研以外でも多くの医学部受験生を指導してきました。
その経験から得た知識をお伝えできたらと思いますので、あなたの受験に役立つポイントがあれば参考にしていただければと思います。
今回の記事を読んで皆さんがゲットできる有益な情報を以下にまとめています。この記事を読んでしっかり下記の内容がわかったか見直しをすることが大事ですよ。
★この記事を読んでわかること
- 今のあなたが岡山大学医学部を受験する生徒層の中でどこに位置しているのか
- 岡山大学の医学部を受験する際にどの科目に注力すれば有利に受験を進め得ることができるか
- どの時期に何をするのが王道なのか
★岡山大学医学部の偏差値及びレベル帯
岡山大学医学部医学科の偏差値はマナビジョン基準で69となっており、全国の高校生の中で上位3%の学力の人が通う学科となっています。
同じレベルの学力の大学としては北海道大学の医学部医学科、京都大学の工学部、大阪大学の薬学部などが挙げられます。非常に受験の難易度が高い大学であることは一目瞭然でしょう。
Q.広島大学の医学部と岡山大学の医学部はどちらの方がレベルが高いの?
偏差値の数値だけを見ると岡山大学と広島大学の医学科のレベルは同列のように見えますが、その実情は大きく異なります。
実は岡山大学の医学科は第二次世界大戦以前からの歴史をもつ旧制6医科大学と言われる大学群に位置している一方、広島大学の医学部は戦前は医科専門学校という立場しかありませんでした。
この歴史の差は皆さんが思っているよりも非常に大きく、中四国の病院で勤務するのであれば、その系列の多くは岡山大学から始まっていることを知っておきましょう。例えば、広島市民病院の母体も実は広島大学ではなく、岡山大学なのです。
このように、医学界における影響力という点においては岡山大学の方が圧倒的に上なのです。ちなみに両学部とも現在の大学長は医学部出身の方であり、どちらも医療に非常に力を入れている大学です。
★偏差値の落とし穴に注意
※ここで注意したいのは国公立大学の偏差値と私立大学の偏差値を同じ扱いにしないことです。私立大学の、特に文系学部は偏差値が実際の大学のレベルよりも高く出てしまいます。高校1年生で文理も決定していない生徒が模試で私立文系学部のA判定をもらったところで、岡山大学の医学部に受かる実力であることとは到底同値にはならないことを肝に銘じておきましょう。
本記事の目次
岡山大学医学部医学科入試状況

まずは医学部医学科の入試について確認してみましょう。
この記事では前期試験について書いていきます。
入試科目・配点
入試科目配点について確認してみましょう。
→入学者選抜要項 2025年度を参考にしています。
| 入試合計点 1650点 | |
| 共通テスト | 個別学力試験 |
| 550点 | 1100点 |
岡山大学の入試配点は以上の内訳からわかるように二次試験に66%が割かれており、いかに二次試験で得点するかが鍵になってきます。しかしこれは一般的な学部の話であり、医学部に関しては必ずしもそうとは言えません。前提として合否の瀬戸際にいる学生は最低でも8割以上共通テストで得点してきます。配点上は二次試験に大きく時間を割くことが大事だと言えますが、共通テストでも最低限の点数は取れるようにしておきましょう。
次に各科目の共通テストと個別学力試験の配点を紹介していきます。
特に大事(8.5割以上の得点をめざしたい)科目については赤文字にしていますので確認しましょう。
| 共通テスト | |
| 国語 | 100点 |
| 英語 | 100点(英検をはじめとした英語資格によって置換可能) |
| 数学 | 100点(1A,2Bどちらも50点ずつの配点) |
| 理科 | 100点(物理、化学、生物から2科目選択) |
| 社会 | 100点(地理探求、日本史探求、世界史探求、公共倫理、公共政経から1科目) |
| 情報 | 50点 |
| 合計 | 550点 |
赤字の科目の多くが個別学力試験でも利用する、つまり理解度をより高くするべき科目です。共通テストであろうとより難易度の高い個別学力試験であろうと揺らぐことのない確かな学力をこれらの科目では養うべきです。
今年から情報が新規科目として追加され50点の配点が振られていますが、そこまで時間をかけることなく点数が取れる教科になっています。不安な方は夏前に一気に理解度を上げると良いでしょう。
| 個別学力試験 | |
| 英語 | 400点 |
| 数学 | 400点(1A,2B,3Cいずれも含む) |
| 理科 | 300点(化学、物理、生物から2科目選択 各150点) |
| 面接 | 点数なし |
| 合計 | 1100点 |
以上を鑑みて、岡山大学医学部医学科最大の特徴は、超理科重視の配点があることだと言えます。さらにいうと、英語も含めると英数理で1400/1650点、割合にしてなんと84.8%を占める配点となっています。
誰がなんと言おうと最優先は、英語数学理科です。
本当に大事なことなのでもう一度表にまとめておきます。
皆さんもコピーするか、書き写して自分の部屋に貼っておきましょう。
常に勉強するときにはここに立ち帰るべきです。
|
|
共通テスト | 個別学力試験 | 合計 |
| 英語 | 100点 | 400点 | 500点 |
| 数学 | 100点 | 400点 | 500点 |
| 理科 | 100点 | 300点 | 400点 |
| 合計 | 300/550点 | 1100/1100点 | 1400/1650点 |
入試結果
入試に合格する上で大事なのは「総合点が最低点を超える」ことです。
よくある間違いとして「共通テストの最低点を超えれば良い」という考え方がありますがこれは間違っています。大事なのは総合点ですから注意しましょう!
合格者の情報を見てみます。前期試験の情報になります。
|
総合点 |
共通テスト |
個別学力検査 |
||||||||||
|
配点 |
最高 |
平均 |
最低 |
配点 |
最高 |
平均 |
最低 |
配点 |
最高 |
平均 |
最低 |
|
|
R5 |
1600 |
1423.6 |
1299.8 |
1225.5(76.6%) |
500 |
469.2 |
428.8 |
375.0 |
1,100 |
871.0 |
989.0 |
781.5 |
|
R4 |
1600 |
1396.6 |
1290.0 |
1212.4(75.8%) |
500 |
462.2 |
423.8 |
361.4 |
1,100 |
953.5 |
866.2 |
782.0 |
|
R3 |
1600 |
1368.1 |
1220.6 |
1133.6(70.9%) |
500 |
443.3 |
405.6 |
359.2 |
1,100 |
933.5 |
735.0 |
815.0 |
以上の情報を参考にするとどの年も最低70%以上の総合点が必要で、確実に合格するためには77%以上の得点率を目指す必要があります。特に昨年度の内容を参考にすると1225.5/1600点、つまり76.6%の得点率が必要になることがわかります。
この点数を考慮すると、先ほど入試科目と配点の中ででてきた数学理科英語については2科目は最低でも80%の正答率を目指さないと、そもそも勝負の土台に立つことはできません。
自分がどの科目で何点の点数を取って合格最低点を超えるのかという点数計画を立てなければ、効率的な勉強をすることができないということは肝に銘じておきましょう!
※今年は情報(配点50点)が新たに加わるのでそこも要注意です!
昨年と同じ得点率だと仮定すると、1263点が必要になります!
受験戦略

受験戦略としては先程考察したように、「理科での失点をできるだけ避け、英語・数学で高く得点すること」が重要ですが、ここで見落としがちなのが共通テスト対策です。
医学部を受験する人にありがちなのが二次試験の勉強ばかりに時間を取られ、共通テスト対策を疎かにしてしまうケースです。あなたもそうではないですか?
多くの受験生を見て思うのは、共通テスト対策をしっかりやれば二次試験の勉強につながり、共通テスト後の対策で効率よく実力がついくと言うことです。
逆に二次試験の勉強をしていれば、自然と共通テストの得点力がつき点数が上がってくるということはありません。共通テストの勉強は二次試験対策の十分条件でしかありません。
ここ数年の共通テストの難易度を考慮すると、センター試験の時代のように二次試験対策をメインに進めることが困難になってきています。数学や英語に関しては素早く読まないとそもそも時間が足りなくなりますし、理科については二次試験と比較しても遜色ないような難易度の問題が出ることも往々にしてあります。
特に、理科でしっかりとした共通テスト対策を行いきちんとした土台づくりを行いましょう。
共通テストの理科が十分に解けるのであれば、二次試験の理科についても対応することは決して難しくないはずです。
理科の選択
ここからは、各論的な話をしていきます。
大前提として、医師を目指すあなたは生物を選択するのが普通なのではないでしょうか?
…と理想論をかざしましたが、よっぽど物理が出来ないということがない限り生物を選択するメリットは受験においてはないでしょう。入学したら、1年目は生物選択が有利だったりもしますが…
というのも理科科目において生物の難易度は高くなりやすい傾向にあります。相対的に化学や物理の難易度は低くなるので、合格を最優先に考えるのであれば生物を選択することは合理的ではないのです。
実際に、多くのの岡大医学部受験生は化学・物理で受験します。
おそらく、それが正解です。
岡山大学の個別学力検査の化学・物理ははっきり言って難しい部類には入りません。9割狙いも可能でしょう。
生物を選択することは大学に入ってから有利に働きますが、合格してからのことは合格してから考えれば良いのです。周りに生物選択の人は一定数いますから、その人たちに聞いてしまえば特に問題はありません。
特段の理由がなければ、化学と物理を使って受験するようにしましょう!
英語対策
英語は医学部受験で肝となる科目です。
おそらく、理科は相当な時間をかけて対策していくことになりますし、正しい努力をしていればある程度点数は伸びてきます。
合格するレベルにある受験生はかなり高得点を取ってくるので、理科で差をつけるのは難しいでしょう。
そこで、差が付きやすいのが英語になってくるわけです。
理系だとどうしても英語が疎かになりがちですが、医学部志望ではそうはいきません。
岡山大学の英語は、標準的なレベルの問題が多く出題形式も特殊なものはほとんどないので、着実に対策すればむしろ安定して高得点を目指せます。得点奪取の戦略としては、選択問題の精度向上、要約や英作文でのできるだけ部分点を多く稼ぐことが出来るような実力をつけていくこととなります。
英作文の内訳は和文英訳問題は2問と、自由英作文問題が1問の合計3題が出題されます。いかに巧い表現を使うかではなく、知っている表現の中からより適しているものを使用するように心がけると点数がアップしますね!
なお、長文問題については早く正確に読むことが要求される点で共通テストの英語の問題と似通っています。必要箇所のチェックの付け方などの長文を読む上での技術を磨いていけば、自然と点数は上がっていくでしょう。
まれに要約問題が出題されることもあるので、その点だけ気をつけましょう。
また、共通テストの対策も考慮に入れる必要があります。個別試験とは毛色の異なる問題が多く、良くも悪くも質より量を要求してくるのが現在の共通テスト英語の特徴です。「個別試験の問題がちゃんと解ける=共通テストで高得点が取れる」とは決してならないことに注意しましょう。
なお英検などの外部検定の資格を利用して、今までは共通テストと個別学力試験の両方を満点扱いにされてきましたが、2026年度の入試からは共通テストのみ満点扱いとなります。とはいえ、実際に英検に換算すると英検1級を取得してやっと満点扱いになるという非常に割に合わないものになっています。あまり外部検定に時間を割く必要はないと言えるでしょう。
理科対策
個別試験の知識問題については、共通テストと比較しても優しい問題が多いです。というのも、共通テストの理科科目は年々難しくなってきており、下手な個別試験と比較しても共通テストの方が難易度が高いということは往々にしてあります。知識を詰める上で共通テスト対策を進めることを非常にお勧めします。
その一方で、記述問題も個別試験では出されるため、別の対策が必要になることもまた確かです。過去問を解いてみてどういう部分が記述で聞かれているかを把握しておくと、日頃の勉強の時から記述で出やすい部分をチェックしつつ進めることができるので非常に効率的だと言えます。
物理については全範囲から満遍なく出される傾向にありますが、波動の範囲がやや難しい傾向にあるので要注意です。
化学についても全範囲から満遍なく出題される傾向は変わりませんが、記述問題や論述問題が中心となっているので必ず過去問を3年分は夏休み前に解くようにしましょう。
生物についても範囲は満遍ないのですが、いかんせん他の2科目と比較すると難易度が上がります。人間の身体機能や神経に関する問題、遺伝子関係の問題といった難易度の高い問題を論述する必要があり、さらにその論述には100字前後の字数制限がついています。指定されたキーワードを用いつつ論述を完成させるには非常に多くの訓練を必要とするでしょう。
教材は学校配布の問題集に加えて重要問題集シリーズを進めると良いでしょう。
さらに発展として物理なら「良問の風」「名門の森」まで着手できると完璧です!
数学対策
岡山大学の数学の難易度も全体としてはそんなに高くありません。問題の難易度及び時間配分を考えても癖があるような特殊な入試科目ではないです。その分、ケアレスミスなどをしてしまった際には周りと大きく差が出てしまいます。また、数3の範囲から出題される問題については難易度がやや上がるので注意しましょう。複素数平面の問題もよく出るので要注意です。時間に余裕がある分、何回も検算を行うようにしましょう。日頃から記述で問題を解答した後に、検算をする癖をつけておくと良いですね。
個別試験の平穏さとは逆に共通テストは時間配分や難易度が高く、マーク試験に慣れる必要があります。文章を読んだ上で設問に取り組む問題も多く、数を多く重ねないと高得点を取ることは難しいでしょう。設問の誘導に乗れないとごっそり点数を落としてしまうので、要注意です!
以上が重要科目の分析になりますが、まだ漠然としているところも多いと思いますので最後に具体的な計画について書いていこうと思います。
受験計画

では、受験計画のモデルをご紹介します。春は基礎、夏に標準~応用、秋は10月頃より徹底した共通テスト対策、共通テスト後に過去問を中心に二次対策が基本戦略となります。
春に行うこと
あなたに上記の実力があった場合、英語について春の時期に行うことは「絶対的な単語量の増加」と「標準レベルの文法・語句問題の繰り返し演習」、「長文選択問題の精度向上」です。
それぞれ具体的どんな教材を使うべきかを紹介します。
単語量の増加については、学校配布の単語帳を完璧にすることが大前提です。ただしユメタンなどはあまり適切ではなく、TARGET1900やシステム英単語のような大学受験の王道英単語帳が良いでしょう。その上で、文章読解と単語の理解度を接続するために速読英単語を進めることをお勧めします。文章を読むスピードも上がりますし、単語の復習もできるので一石二鳥です。
文法の問題集は学校で配られたもので構いません。この時期で完璧に仕上げましょう。
特に語法のパートはよく出題される傾向にあるので、ある程度代表的な表現はまとめておくと今後の勉強が捗りますよ!
また、毎日長文1題は読んでいくようにしましょう。最初の方は速単を毎日2個ずつ進めていくのが良いでしょう。慣れてきたら毎日3個4個と個数を増やせるようになりますよ!
その後は共通テスト大問8レベルにランクアップし、夏前にはMARCH・関関同立レベルの私大の英語が読めているのが理想です。参考書としては、共通テスト予想問題集(2025年度以降)や旺文社の全レベル問題集で対象のレベルの問題を解いていきましょう。
数学については基礎的な問題が乗っている青チャートなどを夏期間に入るまでに3周はしておきたいです。これは3年生の春より以前から進めておくことをお勧めしますが、3年生の春から本格的に勉強を始めた人はこれくらい当たり前にやらないと医学部に現役で合格するのは難しいということを肝に銘じておきましょう。
理科科目についても、学校範囲の予習をすることが必須です。まずは学校教材(リードαやセミナー)を完成させます。完璧になるまで隅々まで繰り返して下さい。この段階から、まとめノートを作り、自分の抜けている知識を書き出してまとめましょう。特に化学については3年生になってから突然学校の授業のペースも上がります。自分で春休み中に先取り学習をしておかないと、その日の復習だけで1日の理科科目の勉強を終えることになってしまいますよ。
物理は単元ごとに勧めていくことをおすすめします。
まず、物理のエッセンスを力学や電磁気など単元ごとに繰り返し行い、完璧になれば次の単元に進むという方法で行っていきます。この段階の勉強は春の段階で終わらせることが出来るよう、計画して下さい。
物理のエッセンスが出来たら、次は良問の風を用いて応用力を養っていきます。
この段階では2〜3単元ごとに繰り返してもいいかもしれません。良問の風も物理のエッセンスも著者は同じなので解説に一貫性があります。分からない分野はエッセンスに戻って基礎の復習を行って下さい。
2年生の余裕のあるうちにやるべきことはこの理科と数学の予習になります。「いずれこういう内容をするから、今ここは必ず必要だ」という意識があると、勉強の質が格段に上がりますよ。
夏に行うこと
夏は大きくレベルアップすることを目標とします。二次試験に必要な能力の養成を始めていきます。
実際夏の勉強は夏休み前から開始するのが理想になります。難関レベルの長文問題を演習しつつ、長文読解の実力を徹底してつけていきます。
★この時点で必ず岡山大学の過去問を3年分は解くようにしましょう。自分が夏の間に何をできるようにするべきかを見つめ直して勉強の目標を定め直すべきです。
長文は春に使った2つの参考書のレベルを上げてもいいですし、英語長文問題精講などのハイレベルな問題集を一冊仕上げるのもいいと思います。早慶や東京・京都を除く旧帝大レベルまで手を伸ばしていいと思います。
ただレベルを上げるだけでなく、音読などを進めてスピードを上げることも非常に大事です。
また、要約の参考書としては、英文解釈要約精講やディスコースマーカー英文読解がいいと思います。この2つには、しっかり要約の手順が載っているので、導入にはもってこいでしょう。
要約に関しては添削を学校・塾の先生にしてもらうことが重要です。
和文英訳についても本格的に進めていきましょう。基礎英作文問題精講のような教材を用いてよく使うフレーズをまとめておくことが大事です。本番その場で機転を効かせることも大事ですが、この時点ではフレーズなどの基礎知識を高めるように心がけましょう。
数学については、夏の時期は、数ⅠAⅡBと数Ⅲに分け、一冊ずつ完成させます。数ⅠAⅡBは理系数学のプラチカ、数Ⅲはチョイスがオススメです。数ⅠAⅡBに関しては必ず夏で終わらせ、チョイスは最低でもA問題まではやりましょう。
秋以降は共通テスト対策が入ってきてなかなか記述の対策は進みません。夏の間にがっつり記述演習を積むことが数学の高得点の秘訣です。もちろん基礎知識が抜けている場合は青チャートなどの基礎問題教材に戻るようにしましょうね!
理科については論述問題のケアをするよりも、基礎知識の徹底と2学期以降の内容の完全理解が優先です。
夏になれば、重要問題集などを用いて演習を行います。分からない問題が出てきたときには質問して速やかに解決することが大切です。この際にも抜けている知識などがあれば、まとめノートへの書き込みは忘れずに。
共通テストレベルの知識問題に対応できるように慣れば、自然と個別試験の知識問題にも対応できるようになります。論述が不安な人は単発の暗記にするのではなく、その仕組みや理屈を理解して記憶するように心がけましょう。過去問を見てどんなふうに論述問題が出ているのかを確認するだけでも、論述問題の勉強法の解像度は上がるはずです。
また物理については欲を言えば、良問の風を終わらし、名門の森や重要問題集といった演習量の多い問題集にまでこの時期に手を出しておきたいところです。
秋に行うこと
前半は夏に行っていた勉強量を継続してこなしていくことが大切です。学校や塾の授業が始まると、演習量が落ちてしまいがちですが、ここで演習量を落とさないことが実力を大きく伸ばすポイントとなります。ただし、解きっぱなしにすることは厳禁です。定期的に復習をして2回目解く時には満点が取れるようにしましょう!
数学は特に、共通テスト対策と数Ⅲチョイスを引き続いて演習していき、共通テストの得点を安定させて下さい。
10月に入ったら共通テスト対策を本格的に行いましょう。
理科科目も数をこなすことが非常に大事です。
出来ることならば、理科基礎にも手を出して演習量を確保しましょう。
ここで、選択問題は間違えない自信が出るくらいまでやっていきましょう。
正直言って、物理の共通テストでは100点を目指していきたいところです。過去問や予想問題集を用いてどんな問題が来ても大丈夫という感覚が出るまで繰り返し演習を行って下さい。間違えた問題は特に何度も復習をするようにしましょう。
その他共通テスト科目
その他の文系科目についてですが、ここで苦しんでいる受験生や国語を苦手とし足をすくわれた受験生を多く見てきました。
しかし、正直言って、文系科目の戦略・計画は人それぞれです。というのも、社会の科目選択も人によって違いますし、国語の基礎能力は個人差がかなりある上に、その伸びも他の教科に比べ、確実性に乏しいです。
ここで言っておきたいのは、受験は総合点での争いになります。
あなたが、どの科目でどれくらい得点すればいいのか計算し、国語・社会でどれくらいの点数が必要なのかを出してみましょう。
その得点を取るのに必要最低限の努力を行って下さい。
実際私は、国語で7割、地理で8割を目標にし、古典と地理の勉強を夏からはじめて秋の共通テスト演習をしっかり行うことで、次第に目標点レベルに落ち着きました。それ以上のレベルに到達できるような努力はあえて行いませんでした。
理科などの重要科目のレベルアップに時間をかけるようにしましょう。
共通テスト後に行うこと
共通テストでしっかりした得点ができたら、二次試験対策を行っていきます。過去問とオープン模試の過去問をかき集め、毎日一年分、計20~30回分こなすことが出来ればいいでしょう。
ここでも、英語は要約や英作文を中心に添削をお願いしましょう。
理科科目については論述対策を行う必要があります。過去問をこなすうちにコツを掴んでくるとは思いますが、基礎知識の抜けが起きないように復習から始めるのが良いでしょう。
数学は数Ⅲをあらためて詰め直しましょう。その後、大量に演習をする中で記述の勘を取り戻すことが大事です。焦らず復習をするように心がけてください。
まとめ

少し長めの記事となってしまいましたが、いかがでしたでしょうか。あなたに役立つ情報があれば、うれしいです。
岡大医学部医学科に入るには受験業界でも伝説・名物となっているような難問を解いていても仕方ありません。
基礎をしっかり固め、共通テスト演習や標準的な問題集を用いて基礎に基づいた確かな応用力を育てることです。
奇想天外な発想や教科書に載っていないような裏技的公式などにとらわれることなく、着実に実力アップをして下さい。
また、参考書などの詳しいやり方などについては、今回省略しました。さらに、この記事に載せた参考書以外にも岡大入試に合うものは、まだあります。
そして、何よりここに書いた戦略・計画並びに参考書の選択があなたに合っているとは限りません。また、学校や塾の授業の活かし方も人によって違ってきます。
大手予備校や塾の授業も上手く活かさなければ、貴重な時間の無駄となってしまいます。
この記事を読んでやることが明確になっていれば、いいのですが、そうでないのであれば、広大研はいつでもご相談に乗らせていただきます。
過去問分析と多くの受験生を指導した経験だけではなく、あなたの今の状況・思いを総合して、あなたが受かるプランを提示します。
少しでも、広大研のことを信じてみたいと思っていらっしゃいましたら、下記よりお問い合わせ下さい。
また、広大研も医学部進学に向けた「広大研医進ゼミ」を運営しています!
広大研は逆転合格をコンセプトとした進学予備校(塾)であり、医進ゼミでは個別指導と自習コンサルティングを中心とするサポートにより、生徒の志望校合格への最短ルートを提供しています。
無料のも行っておりますので、気になる方はお気軽にお問い合わせください!
広大研では無料体験授業を実施しています

浪人ゼミの詳しいカリキュラム、今までの広大研浪人ゼミの実績、広大研の雰囲気をお伝えできると思います。
1年後の大学入学試験までに自分の成績を一番上げられるのはどこか考えてみてください。
ただし、どこへ行ったとしても実際に頑張るのは君自身ですよ。
広大研は「12名限定」で始めていくので、体験のお申し込みはお早めにお願いします。
広大研に少しでも興味を持ってくださった方や、「逆転合格で第一志望合格を狙いたい!」という方は、まずは気軽に無料体験授業にお越しください!
さらに、こちらから無料体験授業に申し込んでくださった人は、入塾金1,000円OFFのキャンペーンも開催中です!
また、岡山大学医学部をはじめとした、医学部進学を目指すためのおすすめ受験予備校の記事も要チェックです!
広島の医学部受験予備校(塾)おすすめ5選【広島の現役医師監修】