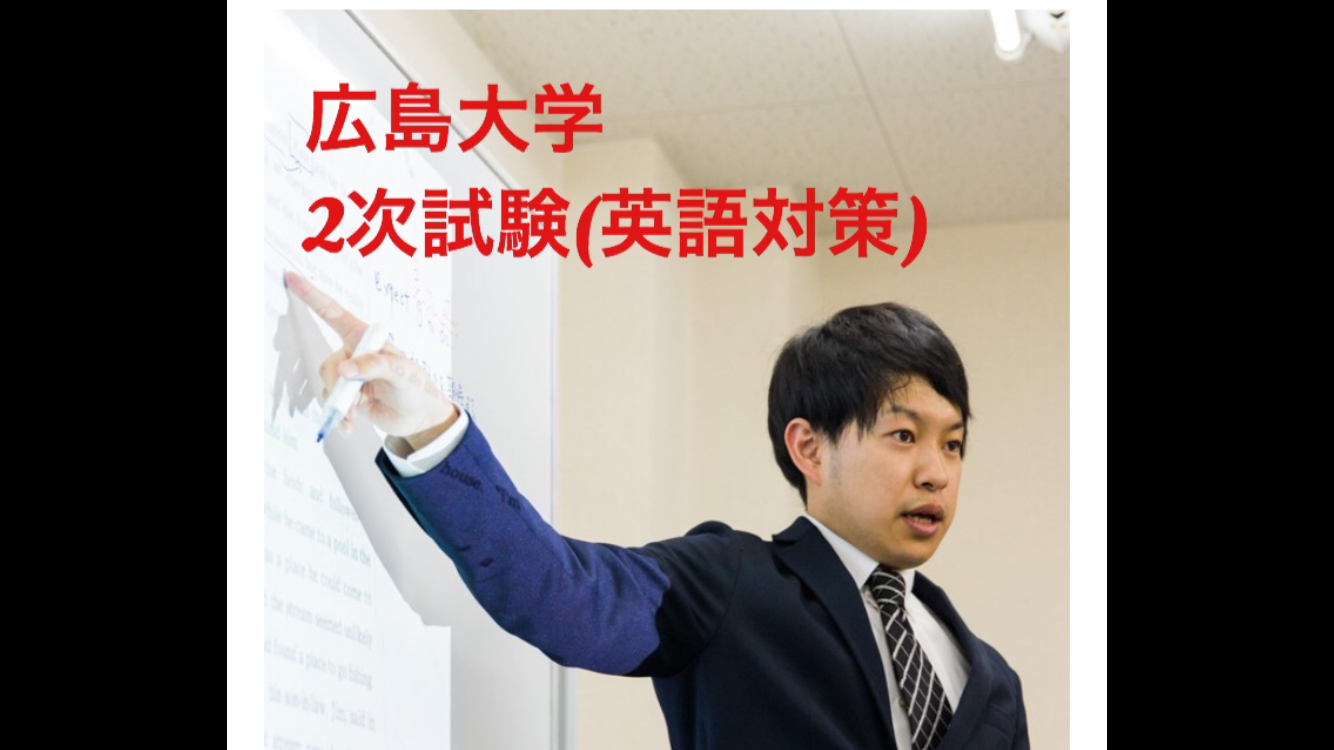広島大学工学部に合格するには?【プロが傾向と対策を解説】

こんにちは。
広大研公式ブログ編集部の梅原壮太(ウメハラソウタ)です。
今回は広島大学工学部合格への傾向と対策についてを2019年度に広島大学工学部に合格した加藤先生に書いていただきました!
広島大学には12の学部の中にたくさんの学科が存在します。
特に理系では、学科ごとに入試の配点が異なりそれに伴って、傾向と対策が異なってきます。
広島大学工学部に合格した経験をもとに「広島大学工学部の入試のシステム」と「どうやって受験勉強をすれば広島大学工学部に合格できるのか」をお伝えしていこうと思います!

※本記事は2019年度に広島大学工学部3類に合格した加藤晴紀が書いた記事です。
本記事の目次
広島大学工学部の特徴
広島大学工学部は、広島県東広島市に位置する広島大学東広島キャンパス内にある、理工系学部の一つです。
工学部は、地域・社会の発展と世界の技術革新に貢献する高度専門職業人や研究者の育成を目的としており、幅広い工学分野を学ぶことができます!
教育と研究は、基礎から応用に至るまで体系的に行われ、卒業後は研究職・技術職として多くの卒業生が国内外の企業、研究機関、公務員など様々な分野で活躍しています。
学部の特徴は、工学の基礎となる数学・物理・化学を重視しつつ、最新のAI、エネルギー、材料、機械、建築、情報、電気・電子、応用化学など幅広い分野をカバーしています!
国際化にも力を入れており、留学制度や外国語での講義、海外研究機関との連携も盛んです。
各課程では、ものづくりや創造性を重視し、実験・実習・プロジェクト型学習などを通して実践力を育成しているそうです。
広島大学工学部は、基礎から応用、国際的な視野までバランスの取れた技術者・研究者を目指す学生にとって魅力的な環境です。
|
科類 |
主な内容 |
概要 |
|
第一類 |
機械・輸送・材料・エネルギー系 |
機械工学、輸送機器、エネルギー、材料工学など、機械とその周辺技術に関する教育・研究を行う。 |
|
第二類 |
電気・電子・システム系 |
電気電子工学、情報通信、制御システム、AI・ロボティクス、次世代エネルギー等の分野を扱う。 |
|
第三類 |
化学・バイオ・プロセス系 |
応用化学、化学工学、バイオテクノロジーなど、化学を基盤とした物質・生命・環境分野に関する学問を学ぶ。 |
|
第四類 |
建築・環境・社会基盤系 |
建築学、都市計画、社会基盤(インフラ)、環境工学など、人間生活と社会を支える空間や基盤の設計を学ぶ。 |
広島大学工学部の入試科目と配点
ここでは、広島大学工学部の入試科目と配点についてご紹介していきます。
科類ごとに配点が違ってくるのでしっかりと確認をしてどの教科にどのくらい注力をしたら良いか見極めるようにしましょう!
広島大学工学部第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系)
広島大学工学部第一類の入試配点は下記のようになります!
共通テスト
| 科目 | 合計点 | 国語 | 地歴・公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 |
| 第一類 | 1000 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 |
2次試験
| 科目 | 合計 | 国語 | 地歴・公民 | 数学 | 理科 | 外国語 |
| 第一類 | 1600 | 600 | 600 | 400 |
広島大学工学部第二類(電気電子・システム情報系)
広島大学工学部第二類の配点は下記のようになります!
共通テスト
| 科目 | 合計点 | 国語 | 地歴・公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 |
| 第一類 | 1000 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 |
2次試験
| 科目 | 合計 | 国語 | 地歴・公民 | 数学 | 理科 | 外国語 |
| 第一類 | 1500 | 500 | 500 | 500 |
広島大学工学部第三類(応用科学・生物工学・化学工学系)
広島大学工学部第三類の配点は下記のようになります!
共通テスト
| 科目 | 合計点 | 国語 | 地歴・公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 |
| 第一類 | 800 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 100 |
2次試験
| 科目 | 合計 | 国語 | 地歴・公民 | 数学 | 理科 | 外国語 |
| 第一類 | 1200 | 400 | 400 | 400 |
広島大学工学部第四類(建築・環境系)
広島大学工学部第四類の配点は下記のようになります!
共通テスト
| 科目 | 合計点 | 国語 | 地歴・公民 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 |
| 第一類 | 1000 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 |
2次試験
| 科目 | 合計 | 国語 | 地歴・公民 | 数学 | 理科 | 外国語 |
| 第一類 | 1200 | 400 | 400 | 400 |
広島大学工学部へ合格するための受験戦略と勉強法
これから、広島大学工学部に合格するためにどのように勉強していけば良いかをお話しします!
どのように勉強するかを把握していないと闇雲に勉強してしまい努力をしていても成績が上がらないといった状況に陥るようになっていきます。
① 行きたい学部の合格者最低点を把握
合格最低点を把握することは、受験戦略を立てる上で不可欠になります。
広島大学工学部に合格するには、各科目の配点を考慮し、効率的に得点を積み上げる必要がある。
例えば、数学や理科が得意なら、それらを武器に最低点を超える戦略を立てることができます。
ただ、数学と理科を得意にしないとそれが難しくなります。
合格最低点という情報をもとに、目標とすべき得点を具体化し、合格可能性を高める学習計画を立てることができます!
②「模試」と「過去問」を利用して現在の学力状況を知る
模試と過去問を活用することで、広島大学工学部の入試傾向を把握し、実戦的な対策が可能になります!
模試は自身の現状を客観的に分析し、苦手分野を特定するために役立ちます!
一方、過去問を解くことで、出題のパターンや難易度に慣れ、本番での対応力を養えます!
これらを組み合わせ、模試の結果を踏まえた学習計画を立て、得点力を向上させることで、合格に近づきます。
③ 合格者最低点と現在の学力状況を比較して、その差を埋めるための学習計画を立てる
広島大学工学部に合格するためには、合格者最低点と現在の学力を比較し、その差を埋める学習計画を立てることが不可欠です!
具体的な点数差を把握することで、どの科目・分野に重点を置くべきか明確になり、効率的な学習が可能になってきます。
また、計画を立てることで学習の進捗を管理し、目標に向けた適切な対策を講じることができます。
このプロセスを繰り返すことで、確実に実力を伸ばし、広島大学工学部合格に近づくことができます!
広島大学工学部へ合格するための科目別対策
ここでは、広島大学工学部に合格するために実際に科目別にどのようなことをすればよいかを紹介しています。
特に必要なのは科目別に自分はどこができているのがそしてどこができいないのかをしっかり把握するようにしてみることが大事です。
そこから下記のやり方を参考に実行してみてください!
英語
広島大学工学部に合格するための英語の勉強法についてこれからお話しします。
英語は先ほど記した入試配点からもわかるように、受験で肝となる科目です。高得点奪取の戦略としては、選択問題の精度向上、要約や英作文でのできるだけ部分点を多く稼ぐことが出来るような実力をつけていくこととなります。この戦略を実践するために必要な計画を細かく見ていきましょう。
どの単語帳であっても、共通テストレベルの範囲は完璧である必要があります。また、文法に関しても、8割程度理解しておく必要があるかと思います。
春に行うこと
では、あなたに上記の実力があった場合、春の時期に行うことは絶対的な単語量の増加と標準レベルの文法・語句問題の繰り返し演習、長文選択問題の精度向上を行っていく必要があります。単語帳や文法の問題集は学校で配られたもので構いません。この時期で完璧に仕上げましょう。
また、毎日長文1題は読んでいくようにしましょう。センターレベルから始めて、夏前にはMARCH・関関同立レベルの私大の英語が読めているのが理想です。
夏に行うこと
夏は大きくレベルアップすることを目標とします。二次試験に必要な能力の養成を始めていきます。夏休み前から開始するのが理想になります。難関レベルの長文問題を演習しつつ、要約や英作文の実力をつけていきます。長文は春に使った2つの参考書のレベルを上げてもいいですし、「英語長文問題精講」などのハイレベルな問題集を一冊仕上げるのもいいと思います。早慶や東京・京都を除く旧帝大レベルまで手を伸ばしていいと思います。
要約の参考書としては、「英文解釈要約精講」や「ディスコースマーカー英文読解」がいいと思います。この2つには、しっかり要約の手順が載っているので、導入にはもってこいでしょう。英作文は、「上級問題特訓ライティング」がおすすめです!
秋に行うこと
秋、前半は夏に行っていた勉強量を継続してこなしていくことが大切です。学校や塾の授業が始まると、演習量が落ちてしまいがちですが、ここで演習量を落とさないことが実力を大きく伸ばすポイントとなります。
10月に入ると共通テスト対策をしっかり行いましょう。過去問や予想問題集を1日1年分解いていきましょう。要約や英作文の演習は少し抑え気味にして、文法・語法問題の徹底的な演習を同時に行っていきましょう。その際には、ランダム系の問題集をするようにして下さい。
ここで、選択問題は間違えない自信が出るくらいまでやっていきましょう。
共通テスト後に行うこと
共通テスト試験でしっかりした得点ができたら、二次試験対策を行っていきます。過去問と毎日一年分、計20~30回分こなすことが出来ればいいでしょう
| レベル | 参考書名 | |
| 基礎レベル | ターゲット1900 | 大学入試に必要な英単語を基礎から確認できます。 |
| 東進レベル別英文法問題集①ー③ | 中学範囲からの英文法の確認と高校範囲の英文法の確認ができます。 | |
| 標準レベル | 英文解釈の基礎70 | 読むために必要な英文解釈のテクニックを学ぶことができます。 |
| 東進レベル別英語長文問題集②ー④ | 基礎レベルから共通テスト、中堅私立大学レベルの長文が読めるようになります。 | |
| 広島大学
合格レベル |
広島大学赤本 | 実際に、出題される広島大学の問題の「傾向」を知ることができます。 |
| 英作文のトレーニング自由英作文 | 自由英作文の書き方が学べ、演習を積むことができます。 |
数学
広島大学工学部に合格するための数学の勉強法についてこれからお話しします。
春に行うこと
私は青チャートを使用し、数学1A2Bの基礎を定着させました。
受験で必要な情報は青チャートにほとんど書いてあり、解き方の指針が書いてあるなど、
数学的思考まで書いてあるため「チャートシリーズ」を使用することをおススメします。
チャートは、基本事項ばかりなので6月末までには終わらせたほうが良いです。
中でも確率、数列、ベクトルは、二次試験で頻出であるため、重点を置いて勉強しましょう。
夏に行うこと
青チャートとチョイスのA問題を使用し、数学Ⅲ重視で勉強をしました。
この時期にセンター模試で1A2Bが7割をとれていたらいいと思います。
夏休みまでに学校の授業ですべての内容が終わらないようであれば、夏休みを使用して予習をしましょう。
広島大学の二次試験の数学の問題は、近年難化傾向にあり、数学3の範囲から多く出題されるため、
早めに数学3の基礎を青チャートでおさえ、チョイスのA問題で一般的な問題に取り組むと良いでしょう。
僕は、単元ごとに青チャート→チョイスのA問題の順番で取り組み、一単元を1・2週間以内に終わらせるようにしていました。
秋に行うこと
数学1A2Bは理系プラチカ、数学ⅢはチョイスのA.B問題を使用し二次試験対策をしました。
アドバイスをしておくと普段から二次試験を意識して、白紙を使用して記述式の解答作成の練習をすることです。
記述式としては、だれが読んでもわかりやすく書くようにしてください。
採点者に書いてあることが伝わらないと意味がないので、計算式を並べるだけでなく、
説明の文章を付け加えるだけで、分かりやすい解答をつくることができ、高得点獲得につながります。
二次試験では数学Ⅲの範囲から微分積分や複素数平面が頻出であるため、そこを中心に勉強をすることをおすすめします。
また、どの単元も証明が出題されていることが多いので、証明問題の演習をしていくとよいでしょう。
個人的にはセンター後は私立対策に時間を割かなければならないと思うので、
秋にどれだけ二次試験対策をすることができるかによって合否が大きく変わると個人的に思います。
冬に行うこと
共通テスト対策として、過去問10年分、進研のマーク総合や、駿台マーク、3年生で受けた模試の解き直しをしました。
過去問については2016年以降の本追試を最低2周解き、センター試験本番で8割以上を目指しました。
共通テスト後に行うこと
自分は過去問、広大オープンの問題集を解いた。苦手な単元はチョイスを復習するとよいです。
二次試験頻出の確率・ベクトル・微分積分・複素数平面をおもに勉強することをおすすめします。
広島大学の数学の問題は、難易度の高いものも多いため、
チョイスのB問題がしっかり解けるようになっておくことが望ましいです。
目標としては、5割を目指していました
理科
広島大学工学部に合格するための理科の勉強法についてこれからお話しします。
私は広島大学工学部第三類で二次試験は物理・化学を選択しました。
そもそも工学部第三類は二次試験で、物理・化学しか選択できません。
高2生で志望校をしっかりと定め、基礎的な内容は日々復習することをおすすめします。
化学
春に行うこと
化学は、大きく分けて理論化学、無機化学、有機化学の3つに分けることができます。
無機化学、有機化学は、まだ学校で習っていないと思うので、学校に合わせて理論化学の勉強をしましょう。
私は「セミナー化学」を使っていたが、基本的には学校で使用している問題集を使用するとよいと思います。
春に理論化学の計算を身につけていないと夏以降に無機化学、有機化学の勉強をする時間がしっかりとれなくなるので、
この時期は計算問題に多く取り組みましょう。
夏に行うこと
私は夏休みを使って先に無機化学、有機化学の暗記をしました。
必ず夏休みに入る前に学校で進度を担当の先生に聞いておく
学校の進度にもよるが、10月末までには理論、無機、有機のインプットを終わらせましょう。
はっきり言うと11月まで有機化学の初修を学校でやるようであれば、受験的には手遅れになる可能性が高いので、
夏休みに自分で予習を進めて暗記しておこう。
学校で10月末までに有機の授業までやってくれるカリキュラムであれば、日々の授業を復習メインで勉強しても良いと思います。
学校の進み具合によって夏休みの勉強が変わってくるので、
化学の先生と話し合っておくか学校は信じずに自分の力で勉強を進めていきましょう。
このときの勉強に関してアドバイスをしておくと、
有機・無機に関しては覚えにくい部分は自分でノートにまとめていつでも見ることができるようにしましょう。
学校で10月末までに有機の授業までやってくれるカリキュラムであれば、日々の授業を復習メインで勉強しても良いと思います。
学校の進み具合によって夏休みの勉強が変わってくるので、
化学の先生と話し合っておくか学校は信じずに自分の力で勉強を進めていきましょう。
このときの勉強に関してアドバイスをしておくと、
有機・無機に関しては覚えにくい部分は自分でノートにまとめていつでも見ることができるようにしましょう。
学校プリントが見にくいのであれば、参考書を1冊買って読むのも良いと思います。
例えば私が使っていたのは「鎌田の有機化学」「福間の無機化学」で
基礎的なことから丁寧に説明してあり非常に分かりやすく、理解しながら暗記できました。
秋に行うこと
私は「化学重要問題集」を使い、広島大学2次試験に向けて応用問題にも取り組みました。
基礎的な内容であるA問題から取り組み、最低でも2周はしたほうがよいです。
もしそれでも解けなかった問題には印をつけ、3周目まで解きなおしましょう。
公式や重要なことが解説に書いてあるため、ノートに書き写してすぐに復習できるようにし、二度間違えることをなくしましょう。
冬に行うこと
共通テスト対策として、過去問10年分、河合マーク総合、駿台マークを使用しました。
過去問については、数学と同様で2016年度から問題形式が変わっているため、
2016年度以降の本追試を最低でも2周は解き、解けなかった問題や重要事項をノートに書き出しました。
大切なのは、自分の頭で考えることなので、
間違えた問題はまず解説を読み込み、わからない場合は、参考書や教科書を使用します。
それでもわからない場合は、先生や友人に聞くという順番を守ってほしいです。
私は演習の目標点としては、初めての問題で8割を目指すように意識していました。
共通テスト後に行うこと
広島大学過去問や重要問題集を使用して、二次試験で6割を目指しました。
有機化学は構造決定の問題が毎年出題されているため、構造決定の練習に力を入れて勉強をすべきです。
理論化学は、酸化還元反応や平衡に関する問題が頻出であるため、そこを中心に勉強するとよいでしょう。
無機化学については、有機化学・理論化学との融合問題として出題されるので、融合問題の練習をすることをおススメします。
物理
春に行うこと
物理は、力学・波動・熱・電磁気・原子に分けられます。
「物理のエッセンス」や学校で使っている問題集を使用して、基本的な力学、波動、熱の復習を行ないましょう。
力学・波動・熱の範囲は6月末までには終わらせるべきです。
これは夏以降に応用問題を解いていく準備なので、できる限り早く終わらせるほうがよいです。
自分は公式をノートにまとめ、振り返りノートを作りました。
これを見るだけでわからない時に問題が解けるように作成しましょう。
物理が特に苦手な人は「橋元の物理をはじめからていねいに」という参考書が、とても丁寧に説明してあり、わかりやすいと思うのでおススメです。
夏に行うこと
「良問の風」を使用して、力学・波動・熱の基礎的な問題に取り組みました。
良問の風には基本的な問題が網羅されているので、共通テスト、二次試験のどちらも対策することができます。
自分は、解けなかった問題に関しては、化学と解き方をノートにまとめ、同じ系統の問題が解けない時に見直すようにしました。
また、学校の進度が遅い場合は、夏休みに物理のエッセンスなどを使用して電磁気学の勉強を進めていくとよいと思います。
秋に行うこと
私は「物理重要問題集」や「名門の森」を使用して応用問題を解きました。
解けなかったところは、物理のエッセンスや良問の風を見直したり、先生や友人に聞くとよいと思います。
問題数をこなしたい人は重要問題集を使用し、解説が詳しく書いてあるものがよい人は名門の森を使用するのがおすすめです。
広島大学の二次試験の物理の問題は、基礎的なものも多いため、良問の風がしっかり解けるようになってから、
重要問題集や、名門の森に取り組むとよいと思います。
また目安として12月は共通テスト対策に時間を費やすので11月までには、電磁気の勉強を終わらせたほうが良いです。
冬に行うこと
共通テスト対策で、過去問10年分、マーク総合、駿台マークを解きました。
上記と同様に過去問は2016年度以降の本追試を最低2周は解き、センター試験で8割を目指しました。
共通テスト後に行うこと
広島大学の過去問と「重要問題集」を解き、二次試験で6割を目指しました。
二次試験では、力学から運動量保存則や反発係数、単振動の問題が頻出であるので、そこを中心に対策をするとよいです。
力学の問題は、基本的なものも多く、高得点を狙っていくべきだと思います。
電磁気からは直流回路や電磁誘導の問題がよく出るが、難易度の高い問題も出るため、徹底的に対策をしましょう。
熱・波動は、比較的簡単な問題が多いため、「良問の風」の問題演習を行い対策しました。
国語や社会について
広島大学工学部に合格するための国語・社会の勉強法についてこれからお話しします。
国語
国語の対策についてですが正直、広島大学工学部を志望する方は国語に注力しすぎる必要はありません!
下の2つのポイントに気をつけて学習をしていただけたらと思います!
- 古文で得点しようとしないこと
- 漢文を長期休みで完成させること
現代文は直前の演習で練習をするようにしたら良いかと思います。
圧倒的にコスパの良い漢文でしっかりと得点を取れるようにすれば安心材料になるかと思います
しっかりと暗記をして対策をしましょう!
社会科目
広島大学工学部を受験することを考え、社会科の選択は「公共、政治・経済」もしくは「地理」をお勧めします。
両科目とも、歴史に比べると暗記量が少なく我々の生活に身近であるという点から得点しやすいと考えます。
- 夏休み以降から共通テスト用のまとめ系参考書を完璧に暗記する
- 直前期に共通テスト演習を10回分以上行い、まとめノートを作成する
を意識して学習を進めてみてください!
全体的な受験戦略方針
広島大学工学部に合格する上で重要なポイントは
「数学」「理科」「英語」に注力する!
「国語」の勉強は不安になるが一旦置いておく
ことになります!
実際に筆者も、二次試験にある英語、数学、物理、化学の4科目に自習のほとんどを費やし、ほかの科目は学校の勉強を徹底しました。
基本的には数学と理科を中心に頑張るといいと思います!
まとめ
数学と理科に関して詳しくまとめていきましたがいかがだったでしょうか。
僕も合格するまで大変でしたが、皆さんも受験勉強頑張ってください!
応援しています!!
広大研では無料の体験授業を実施しています

本記事で、広大研に少しでも興味を持ってくださった方や、「逆転合格で第一志望合格を狙いたい!」という方は、まずは気軽に無料体験授業にお越しください!
さらに、こちらから無料体験授業に申し込んでくださった人は、入塾金1000円OFFのキャンペーンも開催中です!